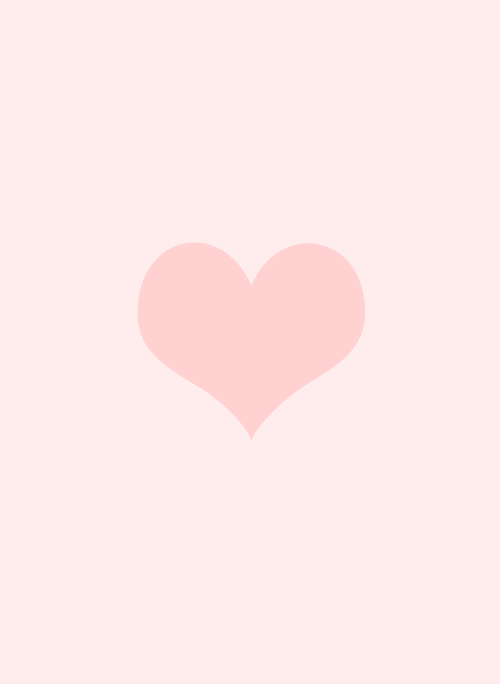言われて初めて気づいた。こみ上げてきていた熱い何かは、遠に涙腺を崩壊させて頬を濡らしていた。
気づいてしまえば脆いもので。溢れ出す涙は止まることを知らない。
「な、んで…、青、いないのお…?」
崩れ落ちるように顔を手で覆う私を棗ちゃんはまた優しく包み込んだ。
こんなに優しくしてもらって、話も聞いてもらっているのに。
私は最低だ。
青の声が聞きたい。
青の温もりがいい。
青の近くにいたい。
もう私は、青に依存してしまっている。
散々泣いて、瞼は真っ赤になってしまった。
棗ちゃんが濡らしたタオルを持って来て、それを目の上に乗せてくれた。
冷たくて気持ちいい…。とろーんとしてきた頭の中で、青の言葉が響く。
゙俺は傍にいるから゙
あんなん結局…嘘だったんじゃんか。
重たくなる瞼にもう逆らう気力もなく、私はそのまま睡魔に身を任せた。
『青も色々隠してるみてえだけど、もう無理だろ。』
『まっきーをこんなにしちゃったんだから。責任取らなきゃぶん殴る。』
恐ろしいような言葉が聞こえた気がしたが、もう瞼を開けることはできたなかった。