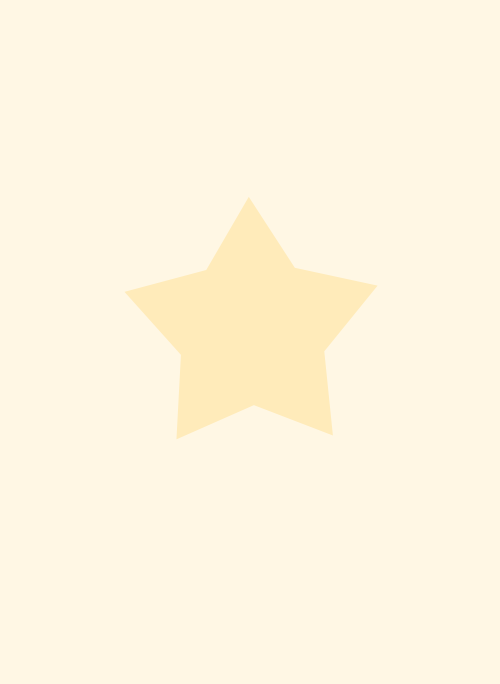孝太は真っ直ぐに自分の席に着いてビジネスバッグを置いた。
そして、パソコンの電源を入れると、コートを掛けるために、あたしの後ろを無言で通り過ぎ、更衣室へと向かった。
その間、ただの一度もあたしを見ることはなく。
僅かに香る孝太の香水が、あたしを透明人間にでもなったような気分にさせた。
まるで、あたしが見えていないとでも言いたげな孝太の素振りに、あたしは挨拶どころか、一言も言葉を発せられなかった。
もう、孝太を見ることさえ怖くて出来ない。
ぬるくなったペットボトルのお茶を口に含んで、居たたまれない気持ちと一緒に飲み込むしかなかった。