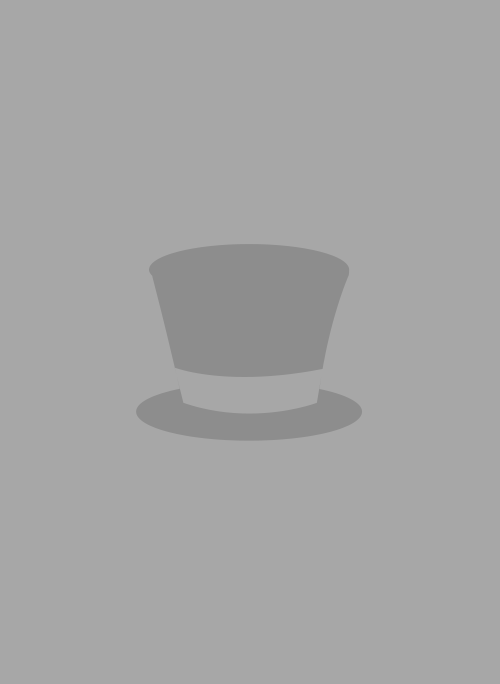「あっ」
その笑顔に見とれたのか、春樹がステップを踏み間違え、恵理夜の足を踏んでしまった。
「も、申し訳御座いません」
――恵理夜は声を上げて笑った。
それに釣られるように、やや困惑しながらも、春樹は微笑んだ。
――曲が終わる。
「……楽しかったわ」
溶けるような、柔らかな笑み――春樹にとっての最上の褒美だ。
「貴女の為ならば」
春樹はそっと、その右手の甲に唇を寄せた。
その笑顔に見とれたのか、春樹がステップを踏み間違え、恵理夜の足を踏んでしまった。
「も、申し訳御座いません」
――恵理夜は声を上げて笑った。
それに釣られるように、やや困惑しながらも、春樹は微笑んだ。
――曲が終わる。
「……楽しかったわ」
溶けるような、柔らかな笑み――春樹にとっての最上の褒美だ。
「貴女の為ならば」
春樹はそっと、その右手の甲に唇を寄せた。