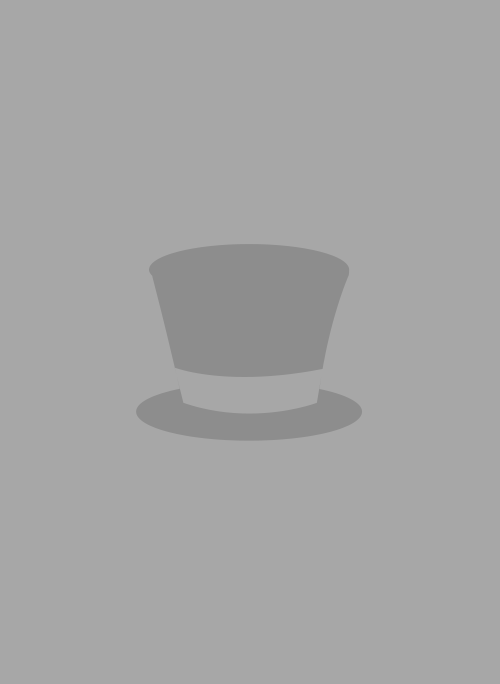先ほど事故でぶつかってしまった少女と少年が、奥まったテーブルでお茶をしていた。
二人とも、仮面をはずし素顔を晒している。
――幸せそうな美しい光景だった。
自分には、決して真似できない少女の無垢な笑顔。
少年の微笑みは、様々な思いを溶かし込んでいるが絶対的な少女の庇護者であることは揺るぎ無い。
嫉妬に似た羨望、そして痛烈な孤独感が恵理夜の胸を突く。
風が吹いて、髪がさらわれた。
彼を思い出す香りがその髪から舞った。
――少年と、目が合った。
二人とも、仮面をはずし素顔を晒している。
――幸せそうな美しい光景だった。
自分には、決して真似できない少女の無垢な笑顔。
少年の微笑みは、様々な思いを溶かし込んでいるが絶対的な少女の庇護者であることは揺るぎ無い。
嫉妬に似た羨望、そして痛烈な孤独感が恵理夜の胸を突く。
風が吹いて、髪がさらわれた。
彼を思い出す香りがその髪から舞った。
――少年と、目が合った。