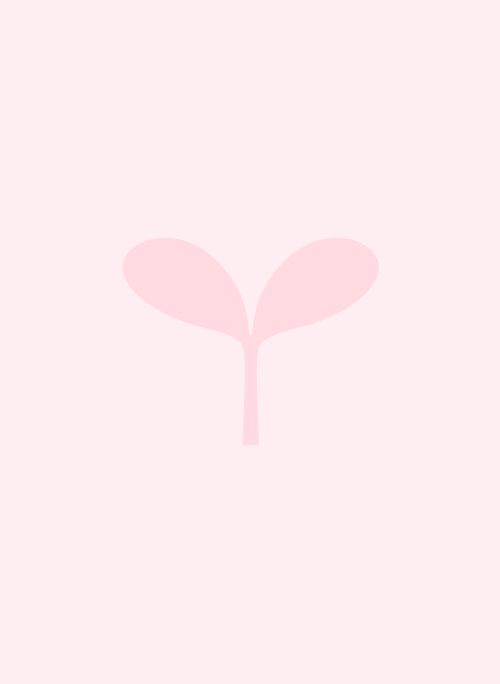沈黙を破ったのはリグだった。
「ねぇ、ヴァージナル」
リグは得意の相手の顔を覗き込むような仕草で、僕の名前を読んだ。
「十三歳で家の仕事を任せられて、いつ戻るかわからないあたしは、立派だと思う?」
リグの質問に僕はすぐに答えることが出来なかった。何て答えたらいいものか、解らなかったからだ。
「僕なんかよりも」
つまらない答えだと思った。
「つまらないなぁ」
リグが言う。
あまりに的確に言われたので、僕は何も言えなかった。僕は下を向いてしまった。
「答えじゃなくて、」
彼女は探偵一族に生まれただけあって、頭が良い。いくら僕が足りない言葉を言っていたとしても、正確に考えを把握してくれる。いまの僕の心境もどうやら察してくれているようだった。リグには隠し事は出来ないな、といつも思う。
「ねぇ、ヴァージナル」
リグは得意の相手の顔を覗き込むような仕草で、僕の名前を読んだ。
「十三歳で家の仕事を任せられて、いつ戻るかわからないあたしは、立派だと思う?」
リグの質問に僕はすぐに答えることが出来なかった。何て答えたらいいものか、解らなかったからだ。
「僕なんかよりも」
つまらない答えだと思った。
「つまらないなぁ」
リグが言う。
あまりに的確に言われたので、僕は何も言えなかった。僕は下を向いてしまった。
「答えじゃなくて、」
彼女は探偵一族に生まれただけあって、頭が良い。いくら僕が足りない言葉を言っていたとしても、正確に考えを把握してくれる。いまの僕の心境もどうやら察してくれているようだった。リグには隠し事は出来ないな、といつも思う。