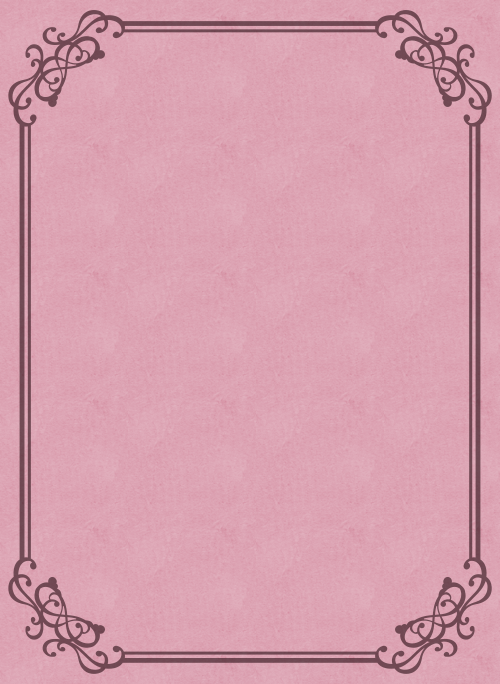「そして通い始めて4年後の3月1日。やっと君は現れた。大学生としてね」
壊れ物を扱うかのように、
彼は私の手にそっと触れた。
「夢みたいだった。
一目であの日の彼女だと分かった。
たとえ君が俺を知らなくても、そんなの関係なかった」
そして啓一は触れるだけのキスを私の唇に落とした。
「啓一……」
私が囁くように名を呼ぶと、彼はもどかしそうに私を見つめた。
言い切れない想いが、彼の中に際限なく溢れていくのが手に取るように分かった。
私の方が彼を愛してる?
そんなこと、あるはずもなかった。
だって彼は、ずっと待っていたのだ。
4年もの間、私だけを。