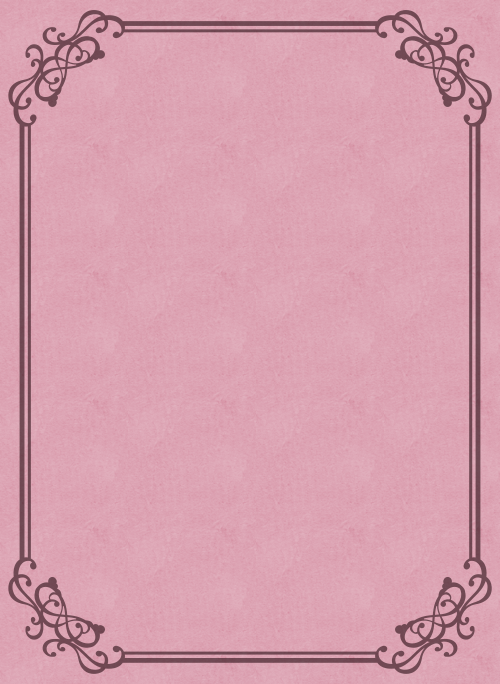「……最初は随分危ない人だな、と思ったよ。変な予言までするし……まぁ顔が好みだったから反論せずに聞いてたけどね」
その言葉に青筋を立てる。
ひどい言い様だ。
「だ……だって現実だと思わなくて!!夢だと思って!!」
そう反論すると笑って彼は、分かってる、と呟いた。
「でもその子があんまり俺を好きみたいだからさ……。顔なんかより、その一途さに、俺もう参っちゃって」
そして彼はゆっくりと瞳を開いた。
「だけど君の名を聞いたら、君は跡形もなく消えてしまった」
そうして私に瞳を移す。
「忘れられるわけなんて、なかったんだ。ずっと君が現れるのを待ってた。毎日ここに通ったよ。出会えなくなるのなんて嫌だったから」
誠実な瞳で、真摯に彼は私を見つめる。