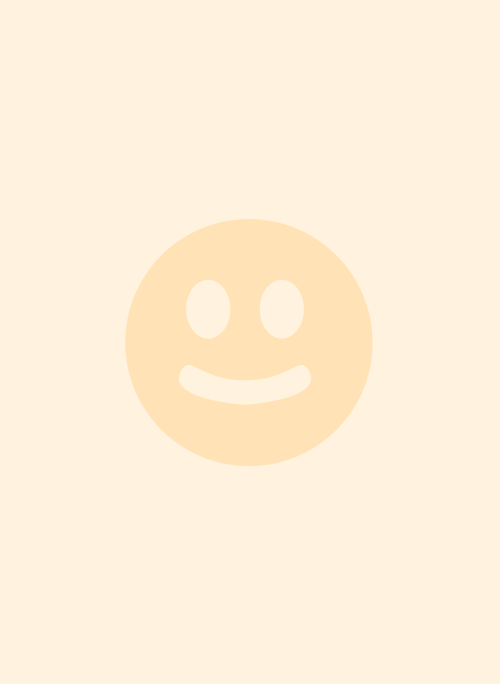「なんでだかわけんねえけど。すげえ、焦った。この一週間、ずっと園崎の口から出た『合コン』がやけに引っかかって。こんな気持ちになるなんて、俺も俺自身が信じられないんだ」
霧島君がポケットから手を出すと、ぎゅっと膝を掴んだ。
「バスケ中心な生活は変わらないし、きっと今まで以上に園崎を苦しめる生活になるのはわかってる。会いたいときに会える保証はないし。普通の恋人同士みたいに、しょっちゅうデートなんてできない。今まで通り、バスケの練習の合間を見て、会うくらいしかできないけれど、それでいいなら……俺たち、付き合わないか?」
私はパッと顔をあげると、霧島君の顔を見た。
「い、今、なんて……」
「二度は言わねえっての」
「だって……そんな、いいの? 私でいいの?」
私は自分の顔を指でさした。
「ああ。俺こそ、園崎に聞きたいくらいだ。俺で本当にいいのか?って。苦しい想いをするのは、園崎なんだから」
「私は、ずっと霧島君が好きだから。付き合うなんて話し自体、夢みたいで……」
私は下唇をぎゅっと噛みしめると、じわっと熱くなる目頭を押さえた。
霧島君がポケットから手を出すと、ぎゅっと膝を掴んだ。
「バスケ中心な生活は変わらないし、きっと今まで以上に園崎を苦しめる生活になるのはわかってる。会いたいときに会える保証はないし。普通の恋人同士みたいに、しょっちゅうデートなんてできない。今まで通り、バスケの練習の合間を見て、会うくらいしかできないけれど、それでいいなら……俺たち、付き合わないか?」
私はパッと顔をあげると、霧島君の顔を見た。
「い、今、なんて……」
「二度は言わねえっての」
「だって……そんな、いいの? 私でいいの?」
私は自分の顔を指でさした。
「ああ。俺こそ、園崎に聞きたいくらいだ。俺で本当にいいのか?って。苦しい想いをするのは、園崎なんだから」
「私は、ずっと霧島君が好きだから。付き合うなんて話し自体、夢みたいで……」
私は下唇をぎゅっと噛みしめると、じわっと熱くなる目頭を押さえた。