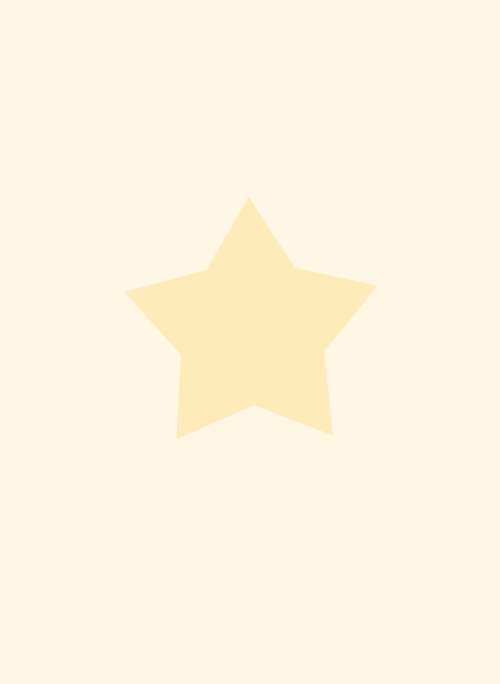「いた……」
「はっ?」
「あの時の奴が、いたような気がした」
「ここにか?」
「うん」
「大丈夫だ。俺がいる限り、お前に手は出せない」
そう言って、伸也さんは私の隣に腰掛けた。
そして、震える私の手を力強く握ってくれる。
「私……」
「あぁ」
「…………」
「吐き出せ。聞いてやるから」
「怖い。毎日、怖い」
「何が?」
「男達が、まだ隣にいるみたいで、学校でも、そのことがバレて、みんなが私をそういう目で見る。そしたら、クラスの女の子まで、男達に見える」
声も体も震えているけど、涙は出なかった。
「他には?」
「こんな思いするなら、殺して欲しかった。死ぬのなんて怖くない」
その言葉を言い終わらないうちに、フワッと温かい体温を感じた。