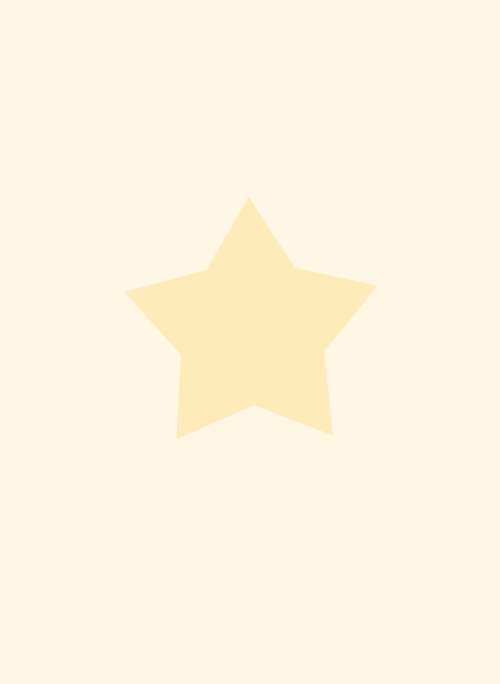私のお気に入りのミルクの入浴剤を入れて、お風呂に入った。
「目腫れすぎだな」
「そんなに?」
「あぁ」
「伸也さん、聞いてた?」
「ドアが少し開いてたから、聞こえた」
「そっか」
「亜美、俺にはお前の気持ちがわかる」
私を股の間に入れて、冷えた私の肩にお湯をかけながら、伸也さんはゆっくりと話し出した。
「うん」
伸也さんは母親に捨てられている。
それも、ゴミ箱に……
伸也さんのお母さんのした行動は、どんな言い訳をしたって、愛情があった行為には思えない。
「でも、俺は亜美に出会って、その傷が癒える気がした」
「伸也さん」
「だから、亜美の傷も俺が癒す。もう少し時間をくれ」
ギュッと抱きしめてくれる温もりと、恥ずかしいくらいの言葉は少しだけ私の心を軽くした。