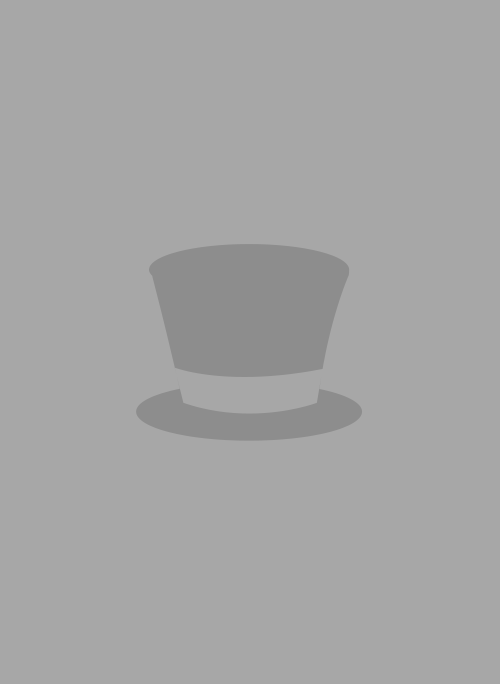「あ…あの!友達が…」
「友達…?」
「昼間、ここに来てる筈なんです。あの…私と同じくらいの背の女の子2人見ませんでしたか…?」
「ここに訪問客は来ない。早くお帰りなさい」
「でも…まだ帰ってないの。もしかしたら、大きなお屋敷だもん、何処かに居ると思うわ」
「私は部屋を一つずつ見て回ってました。そのような子は見ていません。早く帰りなさい」
「でも…」
男の人はどうしても私を帰したいらしい。
この人にクリスが会っていたならこうやって帰ったのかもしれないと思う。けど、実際クリスもリリーも帰ってきてない。
何処かの部屋で、見えないところで眠ってるのかもしれない。私は引き下がれなかった。ジッと男の人を見上げていると、ふと溜息をついて男の人は私の背中を押した。
「私はこの屋敷の主人に仕える身。私の独断では貴方を招待するわけにも行きません。判ってください」
「でも…」
「お客さんかい?」
2階のドアが開きこちらを見下ろしているのは、ガリガリに痩せこけて頬の肉がげっそり落ちた男の人が薄着で立っていた。
「客ならどうして私に声を掛けないのだ、ルーホ」
「すみません、主人はお休み中だと思いましたので」
頭を下げた執事の男の人は俯いた顔で何故か苦しそうな顔をしていた。
「夜遅くに、すいません。私の友達が昼間、ここに来た筈なんです!あの…見てませんか?」
細く痩せ細った男は考え込む様な仕草をしながら私の隣にやってきた。骨と皮だけの手はお祖母ちゃんのそれとは全く違っていて何処か不気味なもののように見えた。
「あぁ、見たよ。薔薇の様に薄く色付いた頬に夕焼けのような髪、夏の夜空のような瞳の女の子だね」
「えぇ!クリスだわ!クリスは今何処に居るの?」
「遊び疲れて奥で眠っているよ。妹も一緒にね」
「2人の両親が心配しているわ。起こして連れて帰らなくちゃ」
「では、2人を起こしに行こうか」
笑ったはずの細い男はクリスの笑顔よりも、お祖母ちゃんの笑顔よりも随分遠いもので、痩せた頬の所為かただの怖いものでしかない。
男はそっと私の背中を押して奥の部屋へと案内してくれた。咄嗟に、執事の男の手を掴むとその手はとても冷たく硬い手だった。
「友達…?」
「昼間、ここに来てる筈なんです。あの…私と同じくらいの背の女の子2人見ませんでしたか…?」
「ここに訪問客は来ない。早くお帰りなさい」
「でも…まだ帰ってないの。もしかしたら、大きなお屋敷だもん、何処かに居ると思うわ」
「私は部屋を一つずつ見て回ってました。そのような子は見ていません。早く帰りなさい」
「でも…」
男の人はどうしても私を帰したいらしい。
この人にクリスが会っていたならこうやって帰ったのかもしれないと思う。けど、実際クリスもリリーも帰ってきてない。
何処かの部屋で、見えないところで眠ってるのかもしれない。私は引き下がれなかった。ジッと男の人を見上げていると、ふと溜息をついて男の人は私の背中を押した。
「私はこの屋敷の主人に仕える身。私の独断では貴方を招待するわけにも行きません。判ってください」
「でも…」
「お客さんかい?」
2階のドアが開きこちらを見下ろしているのは、ガリガリに痩せこけて頬の肉がげっそり落ちた男の人が薄着で立っていた。
「客ならどうして私に声を掛けないのだ、ルーホ」
「すみません、主人はお休み中だと思いましたので」
頭を下げた執事の男の人は俯いた顔で何故か苦しそうな顔をしていた。
「夜遅くに、すいません。私の友達が昼間、ここに来た筈なんです!あの…見てませんか?」
細く痩せ細った男は考え込む様な仕草をしながら私の隣にやってきた。骨と皮だけの手はお祖母ちゃんのそれとは全く違っていて何処か不気味なもののように見えた。
「あぁ、見たよ。薔薇の様に薄く色付いた頬に夕焼けのような髪、夏の夜空のような瞳の女の子だね」
「えぇ!クリスだわ!クリスは今何処に居るの?」
「遊び疲れて奥で眠っているよ。妹も一緒にね」
「2人の両親が心配しているわ。起こして連れて帰らなくちゃ」
「では、2人を起こしに行こうか」
笑ったはずの細い男はクリスの笑顔よりも、お祖母ちゃんの笑顔よりも随分遠いもので、痩せた頬の所為かただの怖いものでしかない。
男はそっと私の背中を押して奥の部屋へと案内してくれた。咄嗟に、執事の男の手を掴むとその手はとても冷たく硬い手だった。