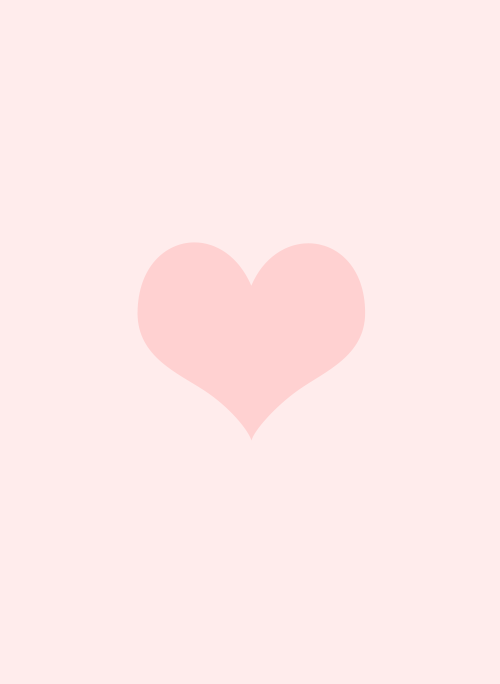「…誰。」
不機嫌を隠すことなく、険を含んだ声で尋ねるとそいつは笑みを崩すことなく答える。
「桐野 暁です。はじめまして、倖浪くん」
優男、紳士的、そんな形容がよく似合いそうな立ち振舞い。
「…で、何。」
…たぶん、いや絶対に。
こいつは好きになれない。
そう確信した。
「うん、話があってね。聞いてくれる?」
「じゃ、聞きたくない。」
「即答だ。」
奴は、クスッと可笑しそうに笑った。
…なんかイラつく。
「…帰ってくれる?」
「話をしてからね」
「…じゃあ何。」
聞こえるように、わざと盛大なため息をついてやる。
しかし奴は、そんなことを気に留める風でもなく、予想外の爆弾を投下して来たのだった。
「俺と、バンドやろう」
…は?
「…なに、それ。」
いきなり、何を言い出すかと思えば。
「んっ?バンド、知らない?」
「…知ってるけど。そうじゃなくて、なんで?」
すると奴は、ふふんと不遜にほくそ笑んだ。
「今、キーボードを探している。けど、なかなかいい人材がいない。」
「…へぇ?で、なんで俺?」
「とぼけたって無駄だよ。俺は知ってるから。キミの音は、俺が望み欲する音だと、ね?」
…なんか、ウザイんだけどマジで。
「聞いたこともないくせに、わかるわけがない。帰って」
俺の拒絶の言葉を聞いて、奴はなぜか笑った。
「それもそうだね。じゃ、聞かせてよ」
「…聞こえなかった?帰って」