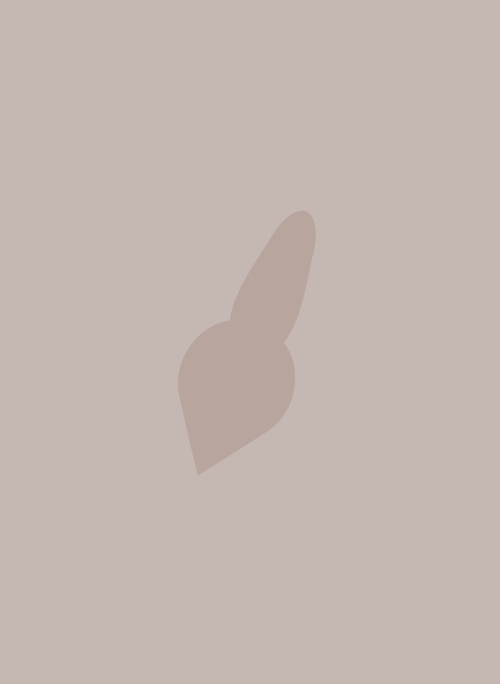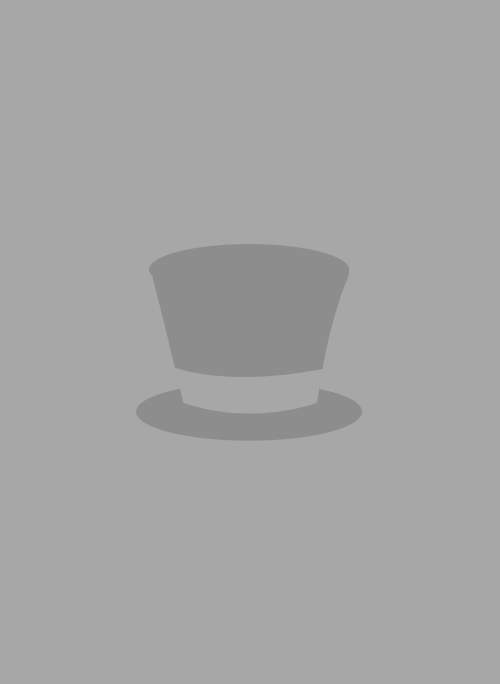また一日が終わる。
時間通りに夕食を食べ、時間通りに入浴し、
そして眠る。
窓の外には満月が覗いている。夜風は夏の割に
ヒンヤリとしている。
「…ン、リン、シャリン」
微かに鈴の音が聞こえる。その音は次第に大きなものとなる。
「こんばんは、素敵なお嬢さん。」
「いつからそこに!?」
鈴の音色に耳をとられている内に黒猫はそこにいた。
「私は黒猫ですよ。足音を消すことぐらい容易い事です。」
口元をクッと上げて微笑む。
「わざわざ足音を消すのね。」
「そうしなければ人間に見つかってしまいますから。」
「私だって人間よ?」
「ふふっ、確かに。」
「あなたは私を見て何を感じましたか?」
答えがなかなか出ない。
「…最初はすごく怖かった。だって喋るんだもの。」
「ふふっ、違いありません。やはりあなたは可笑しな御方だ。」
「喋る事を気にすることがそんなに可笑しいの?」
「いいえ、普通人間は私の事を悪魔の使者だの不吉だのと決めつけます。でもあなたは違う。」
黄金色の眼が優しく光る。
時間通りに夕食を食べ、時間通りに入浴し、
そして眠る。
窓の外には満月が覗いている。夜風は夏の割に
ヒンヤリとしている。
「…ン、リン、シャリン」
微かに鈴の音が聞こえる。その音は次第に大きなものとなる。
「こんばんは、素敵なお嬢さん。」
「いつからそこに!?」
鈴の音色に耳をとられている内に黒猫はそこにいた。
「私は黒猫ですよ。足音を消すことぐらい容易い事です。」
口元をクッと上げて微笑む。
「わざわざ足音を消すのね。」
「そうしなければ人間に見つかってしまいますから。」
「私だって人間よ?」
「ふふっ、確かに。」
「あなたは私を見て何を感じましたか?」
答えがなかなか出ない。
「…最初はすごく怖かった。だって喋るんだもの。」
「ふふっ、違いありません。やはりあなたは可笑しな御方だ。」
「喋る事を気にすることがそんなに可笑しいの?」
「いいえ、普通人間は私の事を悪魔の使者だの不吉だのと決めつけます。でもあなたは違う。」
黄金色の眼が優しく光る。