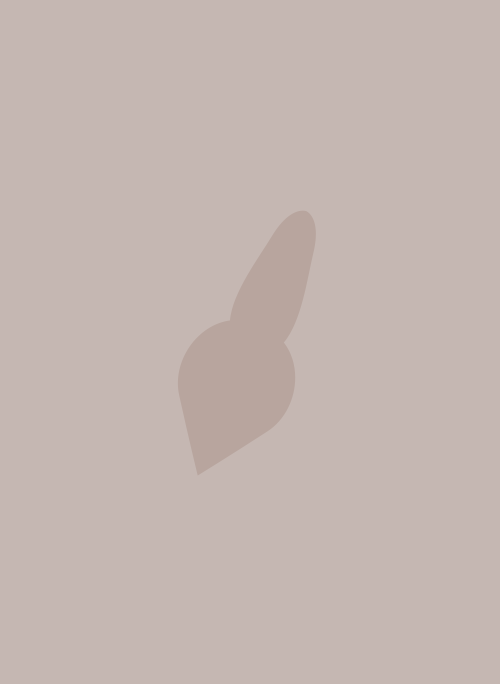「それで賭けバスケをしてたんですね」
「うん。あの頃の俺は胸のあたりに溜まってる何かを発散できれば良かったんだ。だから、加減なんて知らなくてどんどん勝ち続けた。勝てば観衆から必要とされる。その必要とされてる感覚が俺を満たしてくれてたんだ。その時の俺は『自分は誰にも必要とされてない。いらない人間なんだ』って思い込んでたからさ」
先輩は弱々しく微笑んでテーブルに置いてあるアイスコーヒーを飲んだ。
「加減を知らないからストリートを経営してる側の気持ちなんて考えてなくてさ、オーナーと雅サンが仕組んだ試合でボロボロになるまでやられたよ。その時に助けてくれたのが遊汰先輩なんだ」
「少しだけ遊汰先輩から聞きました。観衆の人達からもいろいろされたって...」
「そう。試合中に受けたラフプレーで脳震盪が起きてたんだよね。そのまま倒れた俺は遊汰先輩に家が病院だからって運ばれたんだよね」