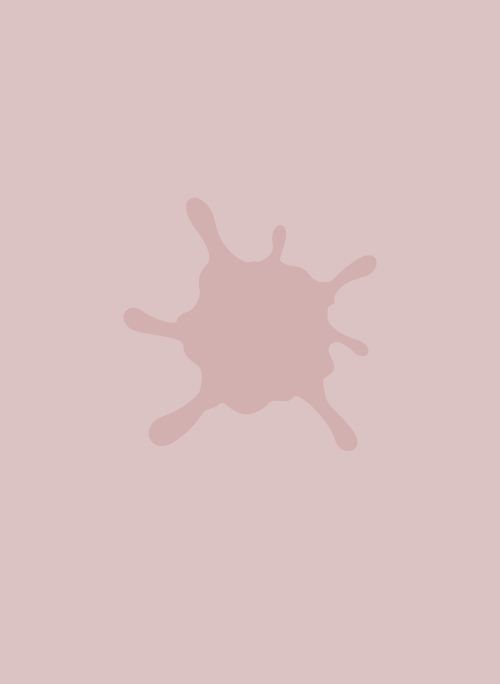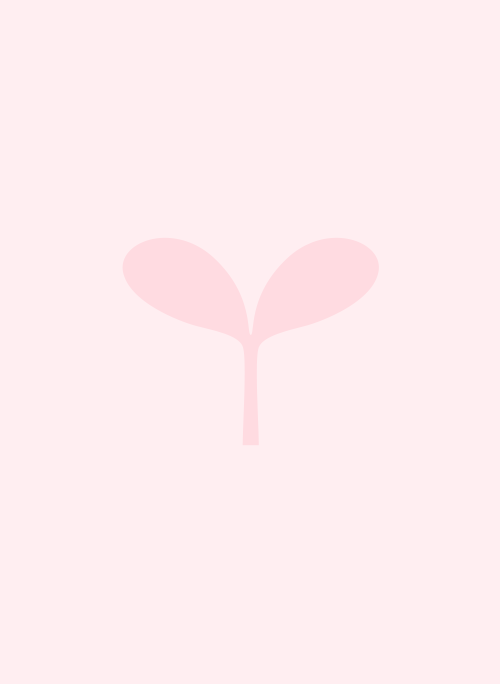「僕は…」
「うん。」
冬彦は夏美の方から目を離し、考えるように話し出した。
「僕は…鍬原さんと…」
夏美の反応はない。
冬彦は、まるで独り舞台の上にいるような感覚になった。
そして、また胸が痛み始め、その苦痛に顔を歪ませながら、声を絞り出した。
「僕は…鍬原さんとは……付き合えません。」
そう言って、冬彦が顔を上げた。
その時、彼の目に飛び込んできたのは、夏美の泣き顔ではなく、夕日を背にしていた夏美が、ゆっくりと、まるでスローモーションのように、斜めに倒れていく瞬間だった。
ガタタンッ!!
何脚かの机を倒しながら、夏美は床に倒れた。
「夏美っ!」
透が険しい顔で、教室に飛び込み、夏美の側に駆け寄った。
冬彦は何がどうなっているのか分からず、呆然と立ち尽くしていた。
窓の外の夕日はもうすぐ落ちそうで、辺りは暗闇に包まれ始めた。
「うん。」
冬彦は夏美の方から目を離し、考えるように話し出した。
「僕は…鍬原さんと…」
夏美の反応はない。
冬彦は、まるで独り舞台の上にいるような感覚になった。
そして、また胸が痛み始め、その苦痛に顔を歪ませながら、声を絞り出した。
「僕は…鍬原さんとは……付き合えません。」
そう言って、冬彦が顔を上げた。
その時、彼の目に飛び込んできたのは、夏美の泣き顔ではなく、夕日を背にしていた夏美が、ゆっくりと、まるでスローモーションのように、斜めに倒れていく瞬間だった。
ガタタンッ!!
何脚かの机を倒しながら、夏美は床に倒れた。
「夏美っ!」
透が険しい顔で、教室に飛び込み、夏美の側に駆け寄った。
冬彦は何がどうなっているのか分からず、呆然と立ち尽くしていた。
窓の外の夕日はもうすぐ落ちそうで、辺りは暗闇に包まれ始めた。