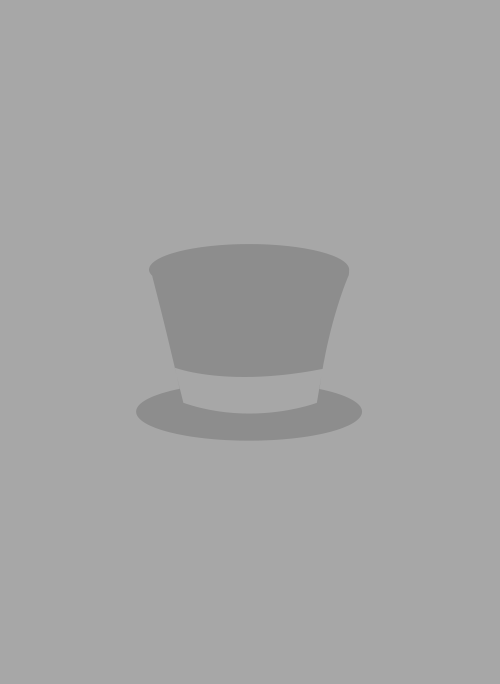「ごめんなさい」
恵理夜は申し訳無さそうに、春樹を見上げている。
「いえ、忘れていった私も悪いですから」
春樹は、何事もないかのようにそれをポケットにしまった。
「春樹、眼鏡なんて掛けてたかしら」
「普段は、問題ないのですが本を読むときなどは」
「ここで、読んでいたの?」
「お嬢様のお帰りを待っていたときに」
静かに、本を読む姿は容易に想像がついた。
ましてや、その整った顔に眼鏡は様になっているかもしれない。
恵理夜は申し訳無さそうに、春樹を見上げている。
「いえ、忘れていった私も悪いですから」
春樹は、何事もないかのようにそれをポケットにしまった。
「春樹、眼鏡なんて掛けてたかしら」
「普段は、問題ないのですが本を読むときなどは」
「ここで、読んでいたの?」
「お嬢様のお帰りを待っていたときに」
静かに、本を読む姿は容易に想像がついた。
ましてや、その整った顔に眼鏡は様になっているかもしれない。