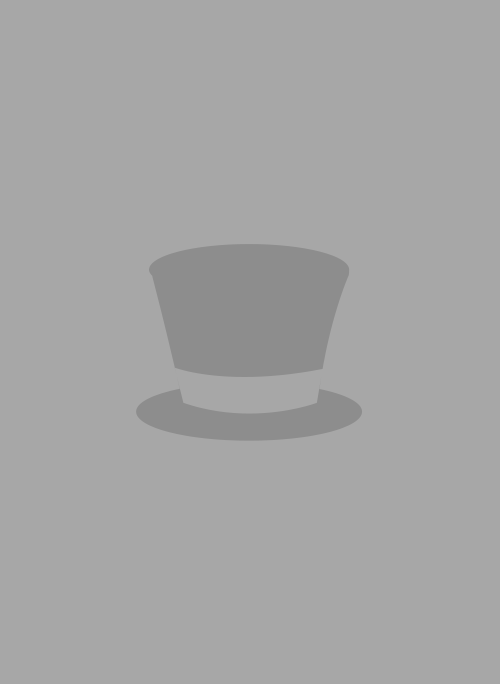「馬鹿」
精一杯の強がり、恵理夜はそっぽを向いた。
「申し訳ございません」
謝りつつ、春樹の表情は緩いままだ。
先ほどの、泣きそうな恵理夜の顔を思い出し、安堵感を覚えていた。
「さあ、帰りましょう」
春樹は、握っていた恵理夜の手を自分のコートのポケットに入れた。
精一杯の強がり、恵理夜はそっぽを向いた。
「申し訳ございません」
謝りつつ、春樹の表情は緩いままだ。
先ほどの、泣きそうな恵理夜の顔を思い出し、安堵感を覚えていた。
「さあ、帰りましょう」
春樹は、握っていた恵理夜の手を自分のコートのポケットに入れた。