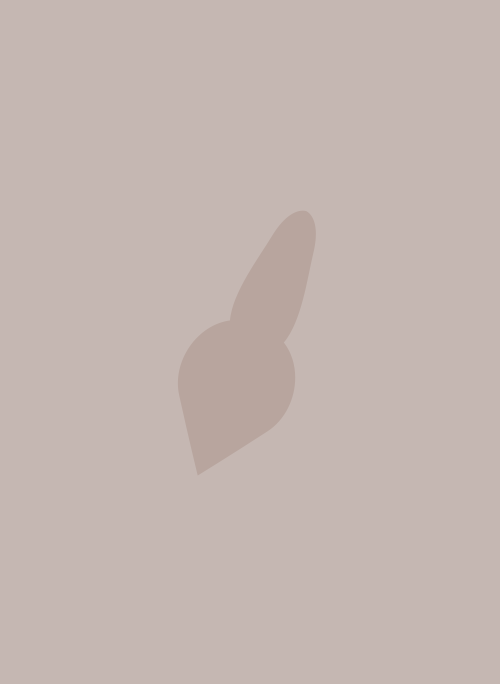「…してるよ。」
里央は優しい瞳をして微笑んだ。
お父さんが子供に語りかける様な声で、そう言った。
「…そっかぁ。」
そっかぁ…、と
何度もその言葉を
噛み締めながら繰り返した。
口元が自然に綻ぶ。
…嬉しい。
この人は野球、続けてるんだ。
白球を追うことを
忘れてはいないんだ。
胸がこそばゆくなり
暖かくなってゆく。
「…桐は、まだ?」
思考が停止する。
桐の名前がでただけで
あたしはこんなにも
反応してしまう。
あたしは
口元を下げ
首をただ横に振った。
里央は
頑固な奴だね、と
困った様に笑いながら、寂しそうな瞳で笑う。
…聞いて欲しい。
桐へのどうしようもない気持ちを里央に聞いて欲しい。
だけど、
桐のいない場所で
野球をやっている人に
桐の話なんてしたら重荷になるだろうか…。
泣き狂った
あの時の記憶を思い出してしまうのだろうか…。
だとしたら…
言えない。
いや
…言わないよ。
「…公、頑張ったね?」
もぅいいんだよ、と
里央は小さくあたしに呟いた。
里央の瞳へと瞳を向ける。
綺麗な漆黒の宝石が
あたしを映していた。
…何で、この人は気づいてしまうんだろう。
いつも、そうだった―
些細な事で人の気持ちを読み取って
その穏やかな性格で、皆を包む。
この人に
このの身を預けられたら、子供のように泣き叫べたら
…どんなに楽だろう。
込み上げてきた気持ちを
必死に堪えた。
泣いてすがりたい気持ちを
必死に堪えた。
里央はあたしの頭の上に
大きな掌をのせて
ポンポンと
優しいリズムを奏でた。
そのゆっくりとした優しいリズムが
あたしの張りつめていた心をほどいてゆく。
あたしは優しさに甘えて
涙こそ流さなかったけど
このどうしようもない気持ちを
里央に打ち明けた―…。
里央は優しい瞳をして微笑んだ。
お父さんが子供に語りかける様な声で、そう言った。
「…そっかぁ。」
そっかぁ…、と
何度もその言葉を
噛み締めながら繰り返した。
口元が自然に綻ぶ。
…嬉しい。
この人は野球、続けてるんだ。
白球を追うことを
忘れてはいないんだ。
胸がこそばゆくなり
暖かくなってゆく。
「…桐は、まだ?」
思考が停止する。
桐の名前がでただけで
あたしはこんなにも
反応してしまう。
あたしは
口元を下げ
首をただ横に振った。
里央は
頑固な奴だね、と
困った様に笑いながら、寂しそうな瞳で笑う。
…聞いて欲しい。
桐へのどうしようもない気持ちを里央に聞いて欲しい。
だけど、
桐のいない場所で
野球をやっている人に
桐の話なんてしたら重荷になるだろうか…。
泣き狂った
あの時の記憶を思い出してしまうのだろうか…。
だとしたら…
言えない。
いや
…言わないよ。
「…公、頑張ったね?」
もぅいいんだよ、と
里央は小さくあたしに呟いた。
里央の瞳へと瞳を向ける。
綺麗な漆黒の宝石が
あたしを映していた。
…何で、この人は気づいてしまうんだろう。
いつも、そうだった―
些細な事で人の気持ちを読み取って
その穏やかな性格で、皆を包む。
この人に
このの身を預けられたら、子供のように泣き叫べたら
…どんなに楽だろう。
込み上げてきた気持ちを
必死に堪えた。
泣いてすがりたい気持ちを
必死に堪えた。
里央はあたしの頭の上に
大きな掌をのせて
ポンポンと
優しいリズムを奏でた。
そのゆっくりとした優しいリズムが
あたしの張りつめていた心をほどいてゆく。
あたしは優しさに甘えて
涙こそ流さなかったけど
このどうしようもない気持ちを
里央に打ち明けた―…。