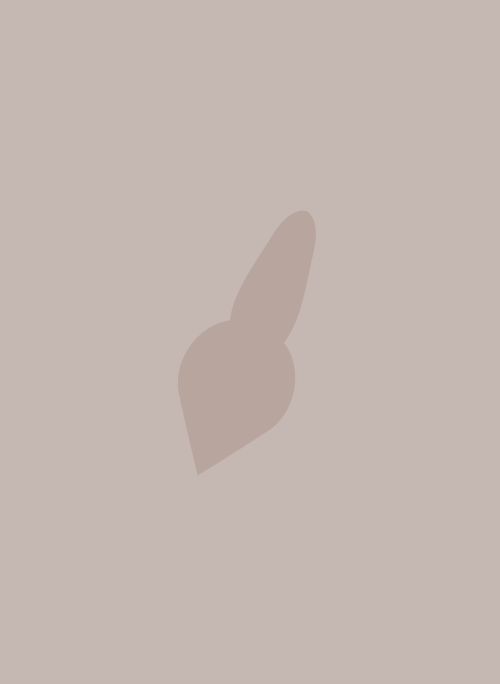六月―
じめじめと肌にまとわりつく湿気。
雨は降り止まず、激しく地面を叩きつけていた。
水溜まりは空を映して
どっちが空か分かったものじゃない。
梅雨の季節は嫌い。
…あいつが
いなくなるから―…
「…橘はまたサボりか。」
朝のHRで
先生が溜め息を溢す。
進級できんぞ、と
愚痴を溢しながらも
探しにいかない先生に、苛立ちを覚えながら
あたしは机に肘をついて
硝子ごしにただ雨を見てた。
目いっぱいに広がる雨は
あまりに降りすぎて姿を変えず
私には写真の様に
止まった光景にみえる。
土砂降りという言葉が相応しい空は
白と黒で埋めつくされていた。
本当に止まったみたいだ。
あの日から―…。
「…あたし、橘を探して来る!!」
机から乱暴に立ち上がる。
ガタッ…と
椅子の倒れる音が静かな教室に響き渡り、児玉した。
視線が一気にあたしへと向く。
クラスメイトの好奇の視線を背中に感じながらも
教室を抜け駆け出した。
渡り廊下に出ると、教室より鮮明に雨の匂いと、居心地の悪い音が、あたしの五感を刺激する。
「…おい、明石………。」
先生の声が遠くに聞こえた。
だけどあたしは聞こえない振りをして、前だけをみて走る。
ほっとけるはずない
雨の日は
あいつが
一人で
泣いている日だから―…