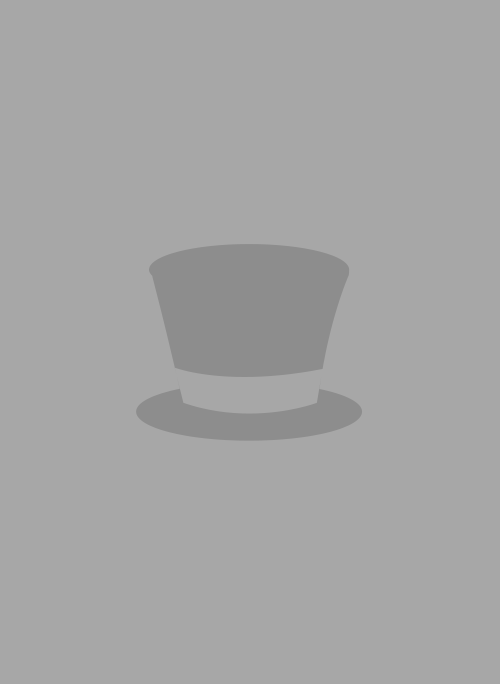「いただけません」
春樹はきっぱりと言った。
「お下がりは、嫌?」
「いえ。これは、貴女が持つべきものです」
「どうして?」
「貴女はご両親の形見をお持ちでない。でしたら、これは最高の形見でしょう」
「そうね」
恵理夜はあっさりと肯定した。
「でも、」
といたずらっぽく笑う。
「モノのなかに二人は居ないもの」
思い出は胸の中にある――そう言ったのだ。
春樹はきっぱりと言った。
「お下がりは、嫌?」
「いえ。これは、貴女が持つべきものです」
「どうして?」
「貴女はご両親の形見をお持ちでない。でしたら、これは最高の形見でしょう」
「そうね」
恵理夜はあっさりと肯定した。
「でも、」
といたずらっぽく笑う。
「モノのなかに二人は居ないもの」
思い出は胸の中にある――そう言ったのだ。