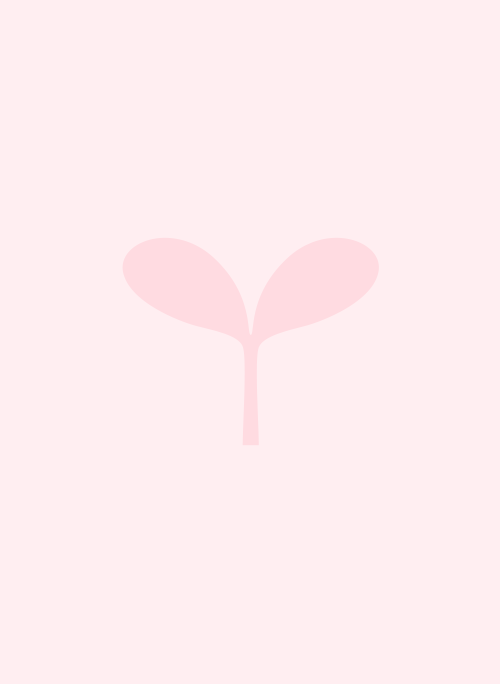多々良は無表情に拳を握った。
王は気難しそうな顔をして、多々良を見据えている。
一方の王妃はおろおろと、自分の夫と息子を忙しなく見比べていた。
「確かか?」
ふと王は視線をはがすと、王妃を振り返った。
「え?」
上の空だった王妃は気の抜けた返事を返す。
「確かに、あれはお前の息子か?」
「そんなの、わかりませんわ。
別れたのはあの子が赤ん坊のときなんですから。」
それもそうだと王はまた多々良に向き直った。
「お前が妻の息子だという証拠は?」
多々良は黙ってペンダントを掲げた。
王も黙って王妃を振り向く。
彼女は唇をわななかせながら、震える声で叫んだ。
「たしかに、私は子どもを預けるときにあれを持たせました!」
家臣たちはざわざわと口々に言葉を交わし始めた。
王だけが落ち着いている。
多々良は真っ向から王の威圧的な視線と対峙した。
「下がれ。」
唐突に、王はそう告げた。
王は気難しそうな顔をして、多々良を見据えている。
一方の王妃はおろおろと、自分の夫と息子を忙しなく見比べていた。
「確かか?」
ふと王は視線をはがすと、王妃を振り返った。
「え?」
上の空だった王妃は気の抜けた返事を返す。
「確かに、あれはお前の息子か?」
「そんなの、わかりませんわ。
別れたのはあの子が赤ん坊のときなんですから。」
それもそうだと王はまた多々良に向き直った。
「お前が妻の息子だという証拠は?」
多々良は黙ってペンダントを掲げた。
王も黙って王妃を振り向く。
彼女は唇をわななかせながら、震える声で叫んだ。
「たしかに、私は子どもを預けるときにあれを持たせました!」
家臣たちはざわざわと口々に言葉を交わし始めた。
王だけが落ち着いている。
多々良は真っ向から王の威圧的な視線と対峙した。
「下がれ。」
唐突に、王はそう告げた。