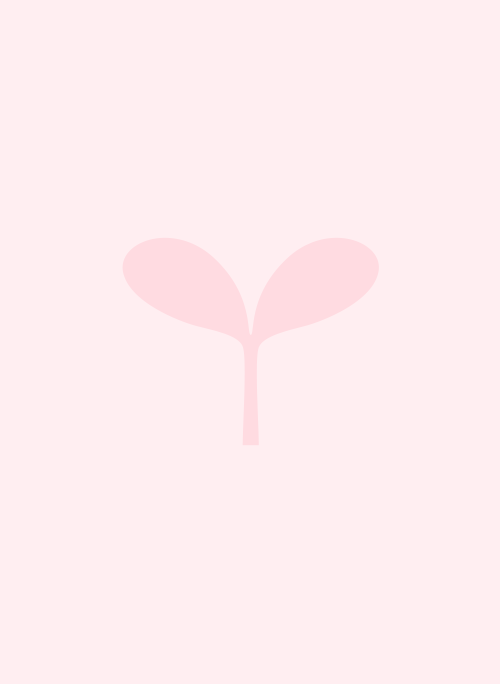あー、もうなんか…。
城って感じだね…。
多々良はぽっかーんとそびえたつ城を見上げた。
隣の呉壽は、不機嫌そうだ。
「ったく、こんなに豪華にする必要があんのかよ。」
「それは僕も同意見。
…孤児院を見せてやりたいね。」
まったく、僕がこの家の生まれだなんて、笑っちゃう。
呉壽は禿げ頭を掻きながら、多々良を見下ろした。
「お前、本当に記憶にないのか?」
「ないよ。
大体、王妃が僕を捨てたのは赤ちゃんの頃なんだろ?
そんなの記憶喪失になってなくったって、覚えてないよ。」
「そうか、そうだな。」
馬鹿なことを訊いたと呉壽は気まずそうだ。
「…じゃ、行くね。」
多々良は深呼吸して言った。
みんなの運命を背負ってかなきゃ、と思うと足が竦んだ。
呉壽は何も言わない。
最後に、前にしてくれたみたいに力強く肩を掴んでくれた。
あぁ、もう。
城に入る前から泣きそうだ。
きっと、もうみんなには会えない。
覚悟してきたはずなのに、やっぱり寂しい。