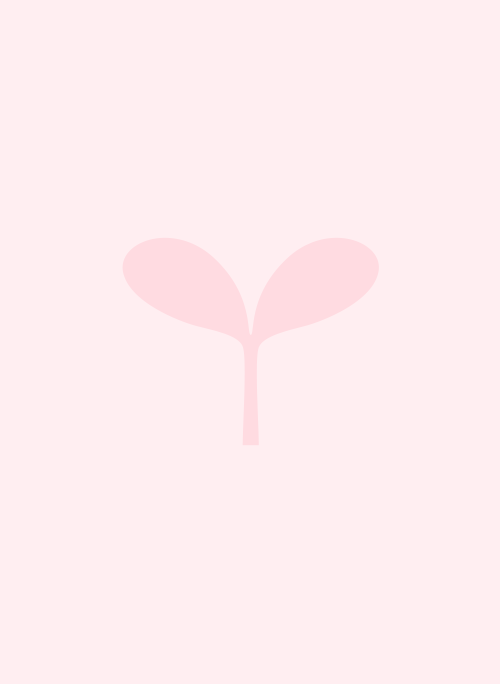愛している。
ぶっきら棒で、乱暴で、女の子らしくなんかないあの架妥が、愛しいんだ。
彼女を愛している。
僕の力でなんとかなるのなら、なんとしてでも助けて見せる。
どんなことだって、する。
「お前は敵だ。」
「…うん…。」
「でも、都楼が信用した男なんだ。
架妥が惚れた相手なんだ。
俺だって、気の置けない奴だと思った。」
今なんて?
多々良はゆっくりと呉壽を見上げた。
「あぁ、言った。
架妥はお前に惚れてるよ。
口に出さなくったって、わかる。
ずっと架妥の世話をしてきたんだからな。」
「待って、そんな素振り僕知らない…。」
「都楼だって気付いてた。
だから、お前を仲間に入れた。
架妥の勘は鋭いから、それを知ってるから、あいつが認めた奴ならって…。」
呉壽はくしゃりと顔を歪めた。
「なのに、お前は王子なんだ。
俺達が最も憎んでいる奴らの仲間なんだ。
頭を奪った、憎むべき相手なんだ!」
「頭を奪った?」
聞き返したが、呉壽は走り去ってしまった。
多々良は呆然としたまま残される。
執拗に都楼が軍を攻める理由。
架妥が嫌悪の色を明らかにする理由。
…それは、父親を奪われたからだったのか。
ぶっきら棒で、乱暴で、女の子らしくなんかないあの架妥が、愛しいんだ。
彼女を愛している。
僕の力でなんとかなるのなら、なんとしてでも助けて見せる。
どんなことだって、する。
「お前は敵だ。」
「…うん…。」
「でも、都楼が信用した男なんだ。
架妥が惚れた相手なんだ。
俺だって、気の置けない奴だと思った。」
今なんて?
多々良はゆっくりと呉壽を見上げた。
「あぁ、言った。
架妥はお前に惚れてるよ。
口に出さなくったって、わかる。
ずっと架妥の世話をしてきたんだからな。」
「待って、そんな素振り僕知らない…。」
「都楼だって気付いてた。
だから、お前を仲間に入れた。
架妥の勘は鋭いから、それを知ってるから、あいつが認めた奴ならって…。」
呉壽はくしゃりと顔を歪めた。
「なのに、お前は王子なんだ。
俺達が最も憎んでいる奴らの仲間なんだ。
頭を奪った、憎むべき相手なんだ!」
「頭を奪った?」
聞き返したが、呉壽は走り去ってしまった。
多々良は呆然としたまま残される。
執拗に都楼が軍を攻める理由。
架妥が嫌悪の色を明らかにする理由。
…それは、父親を奪われたからだったのか。