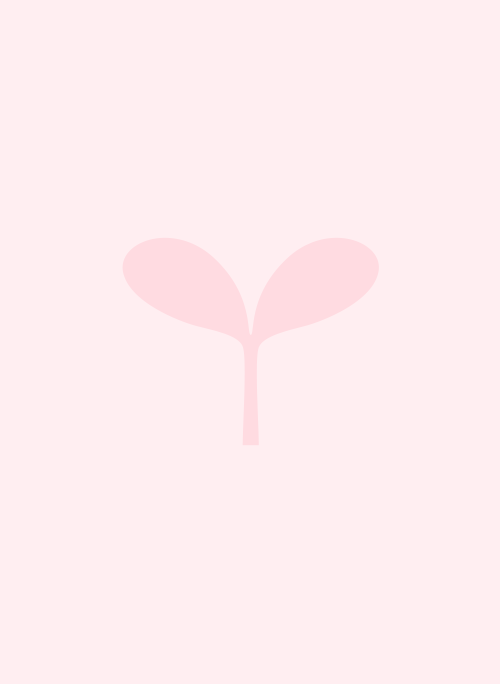パチパチと控え目に燃えるたき火を囲み、多々良は呉壽と無言で食事を摂った。
まだ、呉壽は心を許してくれない。
多々良は上目使いにそっと呉壽をうかがった。
黒い瞳はたき火の光を反射してはいるが、生気はなかった。
「…呉壽は、いつから颪の仲間になったの?」
呉壽はゆっくりと顔を上げた。
「生まれたときから?
それとも、呉壽も僕みたいに拾われた?」
答えてくれないかと諦めかけたとき、呉壽は小さな声で言った。
「拾われた…。」
「そっか。
いくつくらいのとき?」
呉壽はふっと遠くを見つめ、年数を思い返しているようだった。
「お前くらいのときかな。
自分の年齢はわからないから、確かじゃないがな。」
その言葉から、呉壽には親がいなかったことが読み取れる。
多々良は黙って続きを待った。
「架妥から、前の頭の話は聞いたか?」
「ちょっとだけ。」
「おっかない人だった。」
呉壽は掠れた声でわずかに笑い声を漏らした。
「愚かにも、山賊に強盗しようとした俺を力いっぱい殴り飛ばして力の差を見せつけたあとに、『お前、うち来るか?』だなんて言うんだ。」
おっかしいだろ、と今度は自然な笑い声。