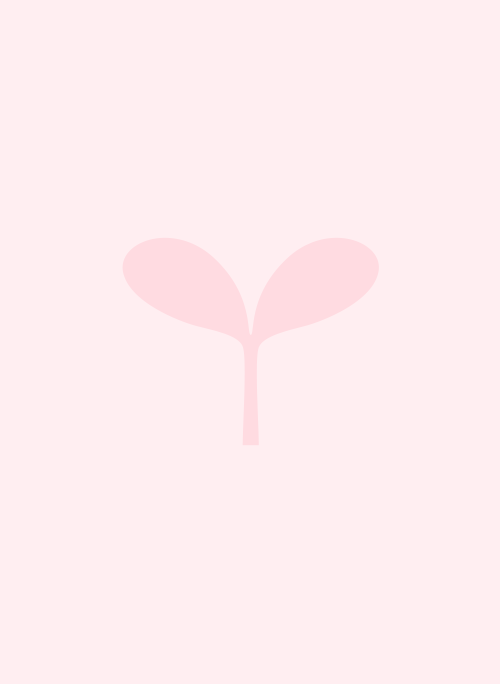*
もう、思考が働かなくなってきた頃、やっと仲間たちが帰ってきた。
都楼を先頭に、疲れ切った様子の男たちは、無言でアジトに姿を現した。
女子供が狂喜して、夫や父親の首っ玉にすがりつく。
一方、見つからない愛する家族を必死になってさがしている者もいた。
多々良もふらりと立ち上がって、見知った顔を探す。
「呉壽…。」
見つけた。
あの、逞しい身体つきは、呉壽に違いない。
多々良は無意識に走り出していた。
「呉壽!」
彼らが出ていってから、初めて発した声だった。
多々良に気付いた呉壽は顔を上げ、疲れた顔で微笑んだ。
「おかえり。
よく無事だったね。」
本当に、よかった…。
「心配かけたな。」
疲労で掠れてはいたものの、呉壽の声は記憶にある通り野太かった。
一段落ついた多々良はきょろきょろとあたりを見回した。
「架妥は?」