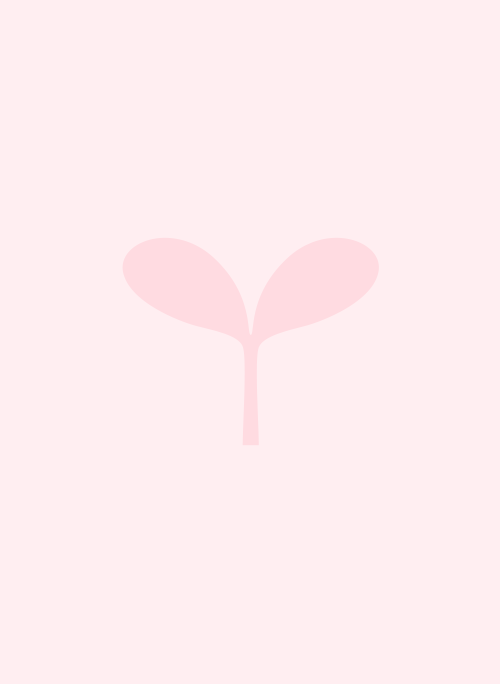爆音で、耳がどうにかなってしまいそうだ。
ビリビリと空気を揺らす振動に、架妥は顔を顰めた。
「あと少し!
もう少し、踏ん張れ!」
敵に押されて退却を余儀なくされた架妥の率いるグループは、じりじりと後退していた。
敵は容赦なく、残党を狩り始める。
もう少しすれば、援軍が来るはずだ。
しかし、さっき送った伝令係が生きているかは怪しい。
少なく見積もっても、相手は自分たちの倍いるのだ。
「もう駄目だ、架妥!」
「弱音を吐くな!」
「だって、ここの地形には奴らのほうが詳しい。」
「あたし達だって、下準備をしなかったわけじゃないだろ!
もう少し行けば、森が濃くなる。
そこまで行けば、逃げ切れる。」
これは半ば自己暗示だ。
確かに、彼の言うことは正しい。
架妥達は圧倒的に不利だ。
でも、都楼が来てくれる。
来てくれるはずだ。
仲間を叱咤しようと顔を上げた架妥の真横に、ことんと何か無機質な音がした。
架妥はゆっくりとそれに目を移す。
手榴弾。
架妥は静かに目を閉じた。