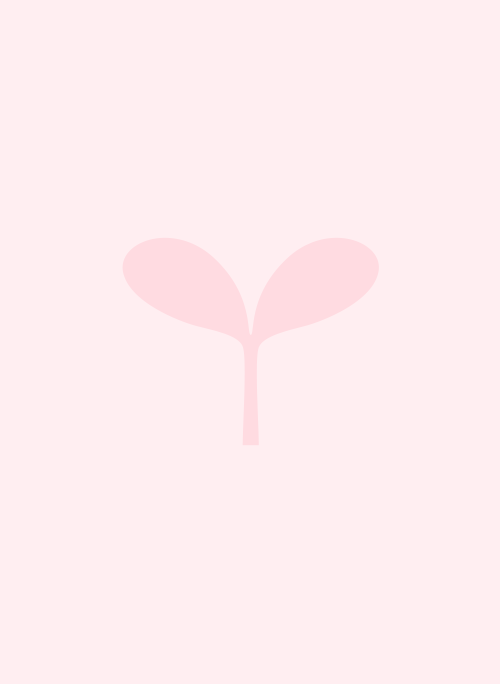冗談なのか、本気なのか。
都楼は架妥に身体をすり寄せた。
重なった肌は、確かに温い。
久し振りに抱きしめられたなと思いつつ、架妥は都楼の胸に頭をすり寄せた。
「ん、確かに。」
「でしょ。
架妥もあったかいね。」
とくんとくん、と都楼の鼓動が聞こえる。
それはいつも通り規則正しくて、静かな音だった。
「架妥。」
「ん?」
「お前が嫌なら、いつでもあいつを追い出すから。」
「いーよ、別に。
あたしも特別あいつを嫌ってるわけじゃないから。」
「そ、ならよかった。」
都楼は最後に意味深な笑みを含んだ声で言って、身体を離した。
「架妥は怒ると怖いからね。」
「それをあんたが言うの?
みんな、何よりも怖いのはキレたあんただと口を揃えていうんだけど。」
「それよりも怖いのは、キレた架妥だってみんなが言ってるの、知ってる。」
架妥はぴたりと動きを止めた。
「え、嘘。」
さぁ、と都楼は歩き去る。
「え、嘘でしょ。
ホントなの!?
ねぇ、都楼!」
本気の追いかけっこを始めた架妥達だった。
都楼は架妥に身体をすり寄せた。
重なった肌は、確かに温い。
久し振りに抱きしめられたなと思いつつ、架妥は都楼の胸に頭をすり寄せた。
「ん、確かに。」
「でしょ。
架妥もあったかいね。」
とくんとくん、と都楼の鼓動が聞こえる。
それはいつも通り規則正しくて、静かな音だった。
「架妥。」
「ん?」
「お前が嫌なら、いつでもあいつを追い出すから。」
「いーよ、別に。
あたしも特別あいつを嫌ってるわけじゃないから。」
「そ、ならよかった。」
都楼は最後に意味深な笑みを含んだ声で言って、身体を離した。
「架妥は怒ると怖いからね。」
「それをあんたが言うの?
みんな、何よりも怖いのはキレたあんただと口を揃えていうんだけど。」
「それよりも怖いのは、キレた架妥だってみんなが言ってるの、知ってる。」
架妥はぴたりと動きを止めた。
「え、嘘。」
さぁ、と都楼は歩き去る。
「え、嘘でしょ。
ホントなの!?
ねぇ、都楼!」
本気の追いかけっこを始めた架妥達だった。