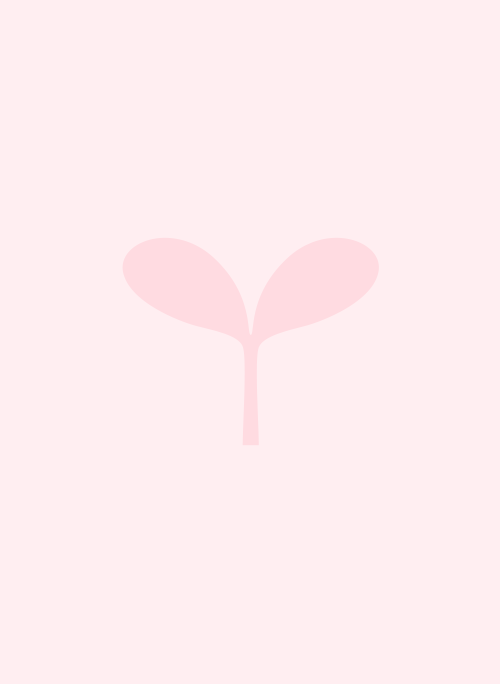都楼の腕が伸びてきて、架妥の頭を撫でる。
架妥はその手に頭をすり寄せた。
「うん。」
返事を返すと、もう一度都楼の手は頭を撫で、そして離れていった。
毎度のことながら、都楼に言い聞かせられると落ち着く。
そうしてもらわないと、感情の制御がきかないときもあった。
自分は都楼に依存している。
仲間は誰も口にしないが、周知の事実だった。
そろそろ自立しなきゃいけないんだけどなぁ…。
架妥はポリポリと頬を掻く。
物心ついたときから都楼がそばにいて、何をするにも一緒だった。
そして、当たり前のように互いに寄り添ってきたため、それは言うほど簡単ではないのだ。
ふと何気なく視線を巡らせると、またあの捕虜と目があった。
ぴきりと顔が引きつる。
このまま、斧、投げてやろうか。
いや、檻があるんだから、刺さらないはずだ。
死なないさ。
本気で投げようと試みたとき、またもや頭上からストップがかかった。
「か~だっ。」
遊びに誘うかのような軽い口ぶり。
しかし、それは紛れもなくお叱りの声だった。
「わかったよぅ。」
架妥は口を尖らせ、都楼に見張られながら斧をふるった。
架妥はその手に頭をすり寄せた。
「うん。」
返事を返すと、もう一度都楼の手は頭を撫で、そして離れていった。
毎度のことながら、都楼に言い聞かせられると落ち着く。
そうしてもらわないと、感情の制御がきかないときもあった。
自分は都楼に依存している。
仲間は誰も口にしないが、周知の事実だった。
そろそろ自立しなきゃいけないんだけどなぁ…。
架妥はポリポリと頬を掻く。
物心ついたときから都楼がそばにいて、何をするにも一緒だった。
そして、当たり前のように互いに寄り添ってきたため、それは言うほど簡単ではないのだ。
ふと何気なく視線を巡らせると、またあの捕虜と目があった。
ぴきりと顔が引きつる。
このまま、斧、投げてやろうか。
いや、檻があるんだから、刺さらないはずだ。
死なないさ。
本気で投げようと試みたとき、またもや頭上からストップがかかった。
「か~だっ。」
遊びに誘うかのような軽い口ぶり。
しかし、それは紛れもなくお叱りの声だった。
「わかったよぅ。」
架妥は口を尖らせ、都楼に見張られながら斧をふるった。