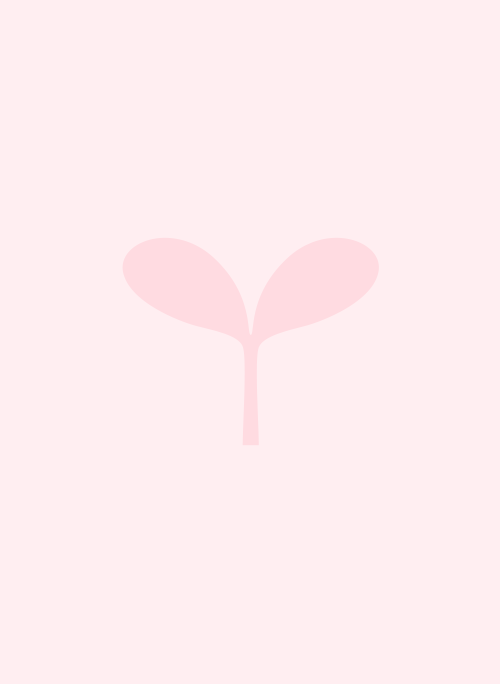*
記憶がない。
それは、思いのほかつらいものだ。
しかし、場合によってはそれが幸いするときもある。
たとえば、自分が孤児の場合。
他の子が親を恋しがって泣く中、多々良は何も感じなかった。
じっと唇を噛んで涙をこらえる友を見て、何を思ったかはもう覚えていない。
ただ、羨ましいと思わなかったことだけは確かだ。
朱色を見て怯えて泣く子どもを見て、記憶がないことを安堵したこともある。
流血を覚えていない多々良は本物の恐怖を感じたことがなかった。
「両親に会いたい?」
何度か訊かれたことがある。
答えは率直にNo。
自分にとっての親は院長だけだ。
他の子はどうかは知らないが、多々良にはそれが真実だった。
院長を父と慕い、
仲間を兄弟として愛した。
…だから、多々良は院を出た。