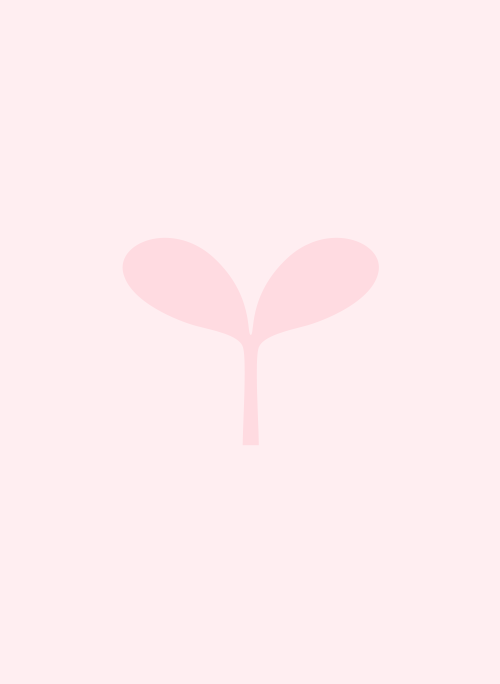昔、彼女が町の長屋で暮らしていた頃とは違って、
向かいの亜鳥は落ち着いた色合いの着物に身を包んで、上品に着飾った格好をしている。
「どういう意味だね?」
今日は城代家老の奥方として会いに来てくれたこの年上の女性は、
相変わらず綺麗で、
そして相変わらず男のような喋り方だった。
私のほうはと言えば──
さすがに時々は女物の着物も着るようになったのだけれど、
お城に戻ってから、
なぜか円士郎に普段は男の格好でいるようにと命じられて──
やっぱり相変わらず小袖に袴だった。
例によって彼女の気味の悪い絵を広げられてはかなわないので、
今はこうして将棋を指していて──
「側室になった気がしないって言うか……結城家にいた時と何も変わらない気がするって言うか……」
私は駒を進めながら、ここ最近ずっと感じていたことをおずおずと口にした。
「もちろん、お城の暮らしは結城家と全然違うけど……
でも、側室にしてもらったのに、エン……殿との関係はあんまり変わってないことに気づいて──
これでいいのかなあって思って……」
向かいの亜鳥は落ち着いた色合いの着物に身を包んで、上品に着飾った格好をしている。
「どういう意味だね?」
今日は城代家老の奥方として会いに来てくれたこの年上の女性は、
相変わらず綺麗で、
そして相変わらず男のような喋り方だった。
私のほうはと言えば──
さすがに時々は女物の着物も着るようになったのだけれど、
お城に戻ってから、
なぜか円士郎に普段は男の格好でいるようにと命じられて──
やっぱり相変わらず小袖に袴だった。
例によって彼女の気味の悪い絵を広げられてはかなわないので、
今はこうして将棋を指していて──
「側室になった気がしないって言うか……結城家にいた時と何も変わらない気がするって言うか……」
私は駒を進めながら、ここ最近ずっと感じていたことをおずおずと口にした。
「もちろん、お城の暮らしは結城家と全然違うけど……
でも、側室にしてもらったのに、エン……殿との関係はあんまり変わってないことに気づいて──
これでいいのかなあって思って……」