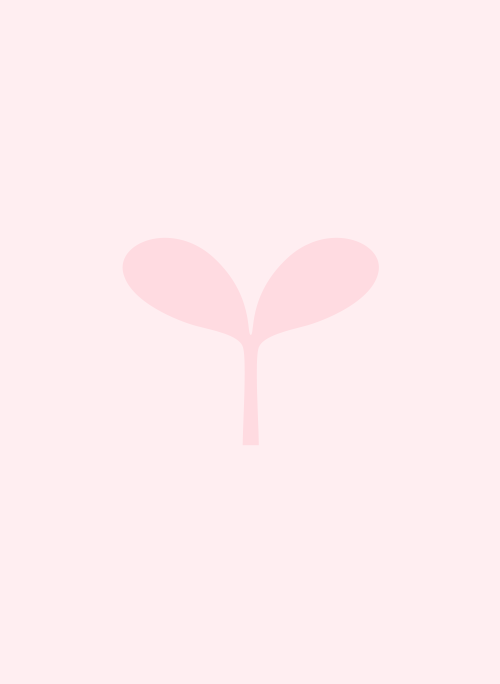「ならばやっぱり、贅沢な料理を作らなくても殿には喜んでもらえそうだな」
「やっぱり?」
「うん、殿には以前、私が長屋で作った鳥料理をお出ししたことがあったのだが、特に豪華な食材を使っていなくても、美味いと言って食べて下さって……」
「え……」
私の手から碁石がこぼれ落ちて、
はっとしたように、亜鳥が口をつぐんだ。
私はぽかんと、亜鳥の顔を眺めた。
「亜鳥さんは、殿に手料理を食べてもらったことがあるの……?」
私は……ないのに。
「ま、待て……!」
私の顔色を見て、亜鳥は慌てた様子になった。
「あ、あの時は、殿に食べてもらうことが目的ではなくてだな、青文殿に出す前に料理の味を見てもらったと言うか……いや、それも無礼な話なのだがね……」
「……そうなんだ」
「おつるぎ様……?」
エンは、亜鳥さんの手料理を食べて、おいしいって言ったんだ。
エン……
私は衝撃を受けてしまって、
何も言えなくなって、
そのうち何だか目がうるうるしてきて──
「殿にも私にも深い意味はなかったのだよ!
頼むからそんな、捨てられた子犬みたいな目で見つめないでくれ……!」
亜鳥が悲鳴に近い声を上げた。
「やっぱり?」
「うん、殿には以前、私が長屋で作った鳥料理をお出ししたことがあったのだが、特に豪華な食材を使っていなくても、美味いと言って食べて下さって……」
「え……」
私の手から碁石がこぼれ落ちて、
はっとしたように、亜鳥が口をつぐんだ。
私はぽかんと、亜鳥の顔を眺めた。
「亜鳥さんは、殿に手料理を食べてもらったことがあるの……?」
私は……ないのに。
「ま、待て……!」
私の顔色を見て、亜鳥は慌てた様子になった。
「あ、あの時は、殿に食べてもらうことが目的ではなくてだな、青文殿に出す前に料理の味を見てもらったと言うか……いや、それも無礼な話なのだがね……」
「……そうなんだ」
「おつるぎ様……?」
エンは、亜鳥さんの手料理を食べて、おいしいって言ったんだ。
エン……
私は衝撃を受けてしまって、
何も言えなくなって、
そのうち何だか目がうるうるしてきて──
「殿にも私にも深い意味はなかったのだよ!
頼むからそんな、捨てられた子犬みたいな目で見つめないでくれ……!」
亜鳥が悲鳴に近い声を上げた。