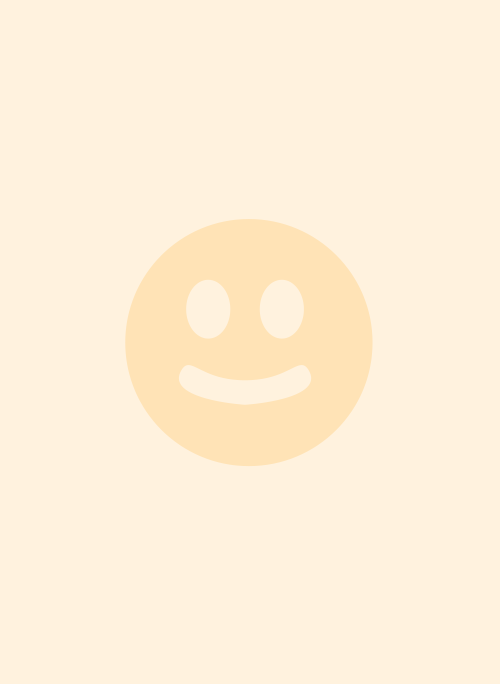その姿を目にした時、スバルはまたもハッとなった。夏期登校日、天風アラシが、隣のクラスをこそこそと覗き誰かの姿を懸命に探していた。
「あいつ…。」
その目は、紛れもない恋の炎を称えた色をしていた。そして、ある特定のショートヘアーの彼女を見つけると、途端に彼はその場からかけ出していた。
「話したいけど、ただ見つめるだけ、か。」
スバルは、とっさにメモ帳を取り出し、サラサラとそう書き連ねた。
そればかりではない。思い出したのだ。いつか、と言っても少し前だが、練習中にヒカルのケータイ電話が鳴った。
「出ていいよ。」
などと声をかけると、彼はディスプレーに目を落とし、パッと頬を赤らめた。直後、受話口から聞えた声は、可愛らしい澄んだ少女のものだったことを。一通り話を終えたヒカルは、ケータイを閉じながらどこか嬉しそうだった。
「みんな、持ってるんだな、恋心って。」
登校日の昼休み、日のあたるベランダで最後の書き直しをした。もう何度も書いて消した紙はなんとなく頼りなさげだった。
「俺だけじゃない、ヒカルの、天風の思いも詞にできたら最高じゃないか!」
背中に太陽を浴びながら、ゆっくりとペンを走らせていった。
「あいつ…。」
その目は、紛れもない恋の炎を称えた色をしていた。そして、ある特定のショートヘアーの彼女を見つけると、途端に彼はその場からかけ出していた。
「話したいけど、ただ見つめるだけ、か。」
スバルは、とっさにメモ帳を取り出し、サラサラとそう書き連ねた。
そればかりではない。思い出したのだ。いつか、と言っても少し前だが、練習中にヒカルのケータイ電話が鳴った。
「出ていいよ。」
などと声をかけると、彼はディスプレーに目を落とし、パッと頬を赤らめた。直後、受話口から聞えた声は、可愛らしい澄んだ少女のものだったことを。一通り話を終えたヒカルは、ケータイを閉じながらどこか嬉しそうだった。
「みんな、持ってるんだな、恋心って。」
登校日の昼休み、日のあたるベランダで最後の書き直しをした。もう何度も書いて消した紙はなんとなく頼りなさげだった。
「俺だけじゃない、ヒカルの、天風の思いも詞にできたら最高じゃないか!」
背中に太陽を浴びながら、ゆっくりとペンを走らせていった。