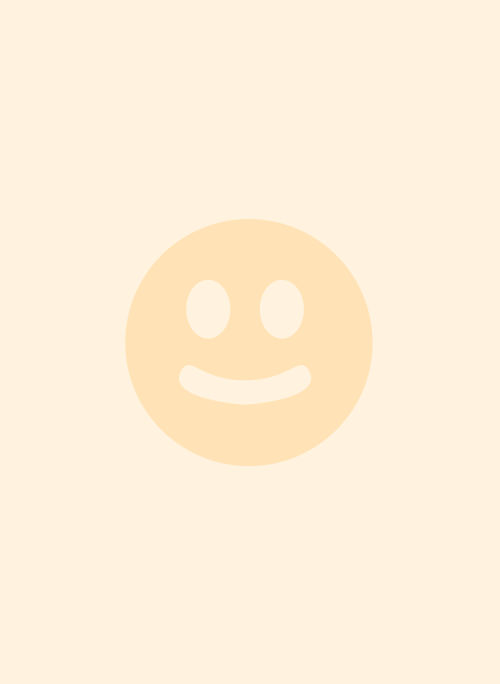「うっさいな、忙しいんだよ、俺は。あんたら庶民とは違うからな。」
「なあに、ごちゃごちゃ言ってんだよ、お前、無理なんだろう。人には散々けちつけといてさ。」
ヒカルは、得意の挑発口調で彼をはやしたてた。アラシは、その横で呆然としているばかりである。
「うっさいっつってんだろう。国語音痴に言われたくないね。いいか、詞を書
くってのはな、中途半端な気持じゃダメなんだよ。何か、誰かに伝えたい強い思いがなくちゃダメなんだよ。」
その口調は、いつもの彼であったが、どこか強がっているような、いつもよりも僅かに低温だった。
「わかんねえな、やっぱ。」
ヒカルはそれだけ言うと、テーブルの上に準備しておいたジャガリコに手を伸ばした。
「そういうもんなの、作詞って。」
アラシが、ぼそりと聞いた。
「も、勿論だよ。天風、あんたは何かないのか?強い思い。」
「ううん、もっと勉強ができるようになりたいとかかな。」
「そりゃごもっともだ。」
「なあに、ごちゃごちゃ言ってんだよ、お前、無理なんだろう。人には散々けちつけといてさ。」
ヒカルは、得意の挑発口調で彼をはやしたてた。アラシは、その横で呆然としているばかりである。
「うっさいっつってんだろう。国語音痴に言われたくないね。いいか、詞を書
くってのはな、中途半端な気持じゃダメなんだよ。何か、誰かに伝えたい強い思いがなくちゃダメなんだよ。」
その口調は、いつもの彼であったが、どこか強がっているような、いつもよりも僅かに低温だった。
「わかんねえな、やっぱ。」
ヒカルはそれだけ言うと、テーブルの上に準備しておいたジャガリコに手を伸ばした。
「そういうもんなの、作詞って。」
アラシが、ぼそりと聞いた。
「も、勿論だよ。天風、あんたは何かないのか?強い思い。」
「ううん、もっと勉強ができるようになりたいとかかな。」
「そりゃごもっともだ。」