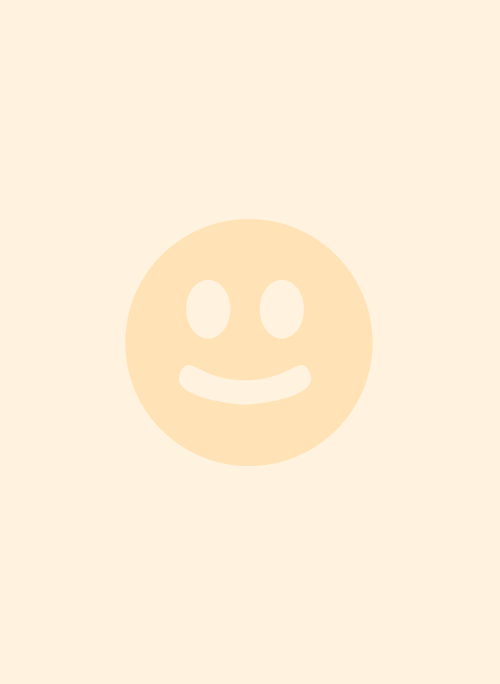「アラ、おはよう」
沈黙を破ったのはあたしでも少女でも無かった。
「おはようございます、おばさん」
真っ赤なワンピースを揺らして振り返る少女、表情は見えなかったがおはようと小さく言っていた。
「久美ちゃん、おはよう。八時よ。トーストが焼けてるわよ」
おばさんは、にこりと微笑み長いスカートにまいてある素敵なエプロンをゆわき直した。
まだ朝なのに…と朝は関係ないか、きょうもおしゃれだ。
おばさんの前に居る少女におばさんは声をかけた。
「ありさちゃん、久美ちゃんとともだち?」
あたしはちょっぴりどきっとした。だってあたしは会って五分もたっていないひとにあたしとその人の関係を言われるのだから。
「あ、いや、さっき知った」
即答で答えた少女は、あたしが予想できなかった答えを返した。もっと、YES・NOとかそういうのだと思った。その言葉にはまだこれから、ともとれる返事だ。そうか、彼女が“ありさ”なのか。
「トースト、はやくおいでね」
「あっ、はい、着替えたら」
そう的確な返事を返したあたしにおばさんは顔で相槌をうって階段を下りて行った。それに、ありさ、もついて下りて行った。
アンティークで揃えられた住みなれない部屋であたしはひとり心臓を重くした。