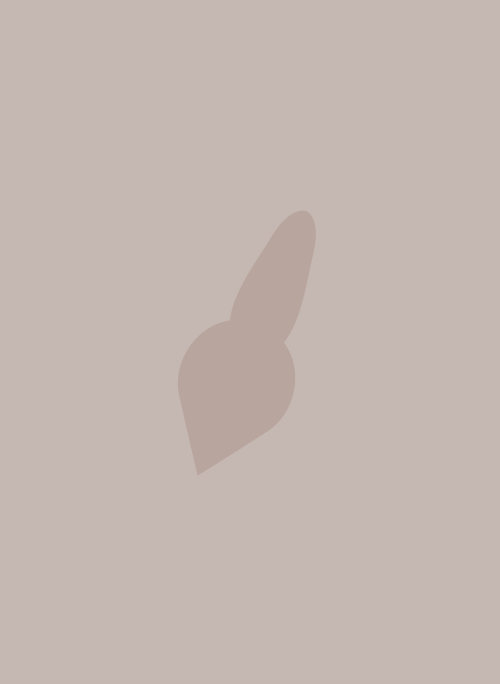「知ってるよ。的場がいつも誰を見てたかなんて。だけどさ、俺諦められない。
俺じゃダメかな?」
斉藤くんが好きだって、知ってるのに言ってくれたんだ。
それでも、想ってくれているんだ。
それでも言わなきゃ。私も前に進まなきゃ。
「ありがとう。でもね、ごめん。やっぱ私…」
「おうっ!分かった。何か悪ィな。困らせちゃった感じで。
もう困らせたりしないからさ。だから…」
まだちょっと好きでいて良い?
ごめんね。ありがとう。
自分でも分からないくらいにぐちゃぐちゃな気持ちに、制御がきかなくて。
泣いてしまった。
泣きたいのは、野山の方だよね。
それでも泣きやむまで傍に居てくれた。
渾身の一発ギャグ。いつもは寒いのに、今は何だかすごく可笑しかった。
「的場はさー、言わないのか?」
落ち着いた私に、空を見上げながら野山は聞いた。
私も同じように空を見上げる。
当たって砕けろ。
嫌いな言葉だった。ついさっきまで。
それも良いかもしれない。
野山の想いを砕いてしまって、分かった。
伝えるだけが苦しいんじゃない。
伝わる方も嬉しくて、悲しいんだ。
「野山のおかげで、決心した。
今から行ってくる」
立ち上がって、スカートの埃をはらった。
野山に背を向ける。
「ありがとう。野山は最強の友達だよ」
あはは、いつものように笑った野山は、声も軽くなっていて。
「褒められてんのか、どうなのか分かんないな、それ」
友達ってのはまずかったかな、と振り返る。
「まー、頑張ってこいや。的場には笑顔が似合うからな」
ピースサインを揺らしながら、言ってくれた。
また泣きそうなのを堪えて、私もピースをした。
何処だろう。
斉藤くんの背中だけを探して走る。
靴箱に靴が無いのを確認して、校舎を出た。
涙のあとに冷たい風がしみて少し痛かった。
俺じゃダメかな?」
斉藤くんが好きだって、知ってるのに言ってくれたんだ。
それでも、想ってくれているんだ。
それでも言わなきゃ。私も前に進まなきゃ。
「ありがとう。でもね、ごめん。やっぱ私…」
「おうっ!分かった。何か悪ィな。困らせちゃった感じで。
もう困らせたりしないからさ。だから…」
まだちょっと好きでいて良い?
ごめんね。ありがとう。
自分でも分からないくらいにぐちゃぐちゃな気持ちに、制御がきかなくて。
泣いてしまった。
泣きたいのは、野山の方だよね。
それでも泣きやむまで傍に居てくれた。
渾身の一発ギャグ。いつもは寒いのに、今は何だかすごく可笑しかった。
「的場はさー、言わないのか?」
落ち着いた私に、空を見上げながら野山は聞いた。
私も同じように空を見上げる。
当たって砕けろ。
嫌いな言葉だった。ついさっきまで。
それも良いかもしれない。
野山の想いを砕いてしまって、分かった。
伝えるだけが苦しいんじゃない。
伝わる方も嬉しくて、悲しいんだ。
「野山のおかげで、決心した。
今から行ってくる」
立ち上がって、スカートの埃をはらった。
野山に背を向ける。
「ありがとう。野山は最強の友達だよ」
あはは、いつものように笑った野山は、声も軽くなっていて。
「褒められてんのか、どうなのか分かんないな、それ」
友達ってのはまずかったかな、と振り返る。
「まー、頑張ってこいや。的場には笑顔が似合うからな」
ピースサインを揺らしながら、言ってくれた。
また泣きそうなのを堪えて、私もピースをした。
何処だろう。
斉藤くんの背中だけを探して走る。
靴箱に靴が無いのを確認して、校舎を出た。
涙のあとに冷たい風がしみて少し痛かった。