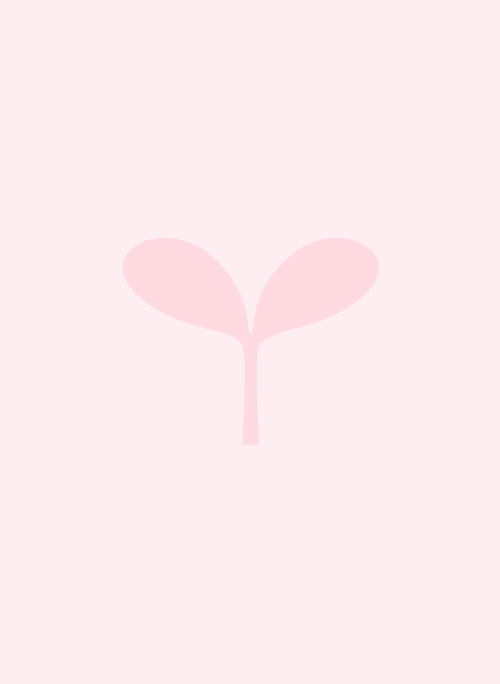「幼稚園から呼び出しがなくて良かったー」
携帯をパチンと閉めて笑うアキは20代前半の女の子にしか見えない。
周りにいる男性もチラチラとアキに視線を走らせる。
私も隣にいるアキを見る。
頭から足先まで完璧に私コーデのアキは一分の隙もなく可愛い女の子である。
あぁ、アキ、可愛いよ、アキ。
一介の主婦をここまでに仕立て上げてしまう自分の才能が怖い。
「で、今からだけど」
ハルが口火を切った。私は姿勢を正す。
このミッションは言うならば絶対に負けられない戦いなのだ。
アキは巻き込まれただけだけど、予想以上に自分が可愛くなったので気合が入ったらしく、私と一緒にハルの方に乗り出して話を聞く。
「向こうに着くとちょうど昼休み時なのよね。だから会社から出てくるのを待ち伏せするか…」
「いや、それはちょっと待って」
アキが小さく挙手。
「会社の前だと誰に見られてるか分からないからちょっと…ソラ君の立場もあるし」
「あぁ、そうか」
ハルはその言葉に2、3頷き、スケジュール表を開き、何か見つけたようにあ、と小さく声を出した。
「アキ、今日は冬野君が本を買う日だわ」
「何?あいつ毎月本買ってるの?ハルんとこで?ヤンジャン?」
事情を知らない私が聞くと、
「いや、それ週刊だから。しかもそれ冬野君立ち読みしてるし」
と、ハルにさらりと突っ込まれる。
しかも余計な情報が付いてきたので、アキがごめんと謝った。誤爆である。
ハルは立ち読みの件は気にしてないらしく、アキの謝罪を聞き流して時計に目をやった。
「冬野君、いつもお昼休みに来るから今から行けば間に合うかも。本屋の前で待ち伏せはどうかな?」
「ああ、本屋の子になりすまして、いつも見てました、好きです、みたいな?」
ハルの案に乗り、シナリオを口にしながら、絵面を想像する私。
「そうそう。何だったら冬野君を見つけて出てきました風の演出を醸し出すために、私のエプロンつけて。」
赤い簡素なエプロンをつけて冬野を追いかけるアキ。
うん、可愛い。悪くない。
「よいではないか。それでいこう」
気分は演出家である。
携帯をパチンと閉めて笑うアキは20代前半の女の子にしか見えない。
周りにいる男性もチラチラとアキに視線を走らせる。
私も隣にいるアキを見る。
頭から足先まで完璧に私コーデのアキは一分の隙もなく可愛い女の子である。
あぁ、アキ、可愛いよ、アキ。
一介の主婦をここまでに仕立て上げてしまう自分の才能が怖い。
「で、今からだけど」
ハルが口火を切った。私は姿勢を正す。
このミッションは言うならば絶対に負けられない戦いなのだ。
アキは巻き込まれただけだけど、予想以上に自分が可愛くなったので気合が入ったらしく、私と一緒にハルの方に乗り出して話を聞く。
「向こうに着くとちょうど昼休み時なのよね。だから会社から出てくるのを待ち伏せするか…」
「いや、それはちょっと待って」
アキが小さく挙手。
「会社の前だと誰に見られてるか分からないからちょっと…ソラ君の立場もあるし」
「あぁ、そうか」
ハルはその言葉に2、3頷き、スケジュール表を開き、何か見つけたようにあ、と小さく声を出した。
「アキ、今日は冬野君が本を買う日だわ」
「何?あいつ毎月本買ってるの?ハルんとこで?ヤンジャン?」
事情を知らない私が聞くと、
「いや、それ週刊だから。しかもそれ冬野君立ち読みしてるし」
と、ハルにさらりと突っ込まれる。
しかも余計な情報が付いてきたので、アキがごめんと謝った。誤爆である。
ハルは立ち読みの件は気にしてないらしく、アキの謝罪を聞き流して時計に目をやった。
「冬野君、いつもお昼休みに来るから今から行けば間に合うかも。本屋の前で待ち伏せはどうかな?」
「ああ、本屋の子になりすまして、いつも見てました、好きです、みたいな?」
ハルの案に乗り、シナリオを口にしながら、絵面を想像する私。
「そうそう。何だったら冬野君を見つけて出てきました風の演出を醸し出すために、私のエプロンつけて。」
赤い簡素なエプロンをつけて冬野を追いかけるアキ。
うん、可愛い。悪くない。
「よいではないか。それでいこう」
気分は演出家である。