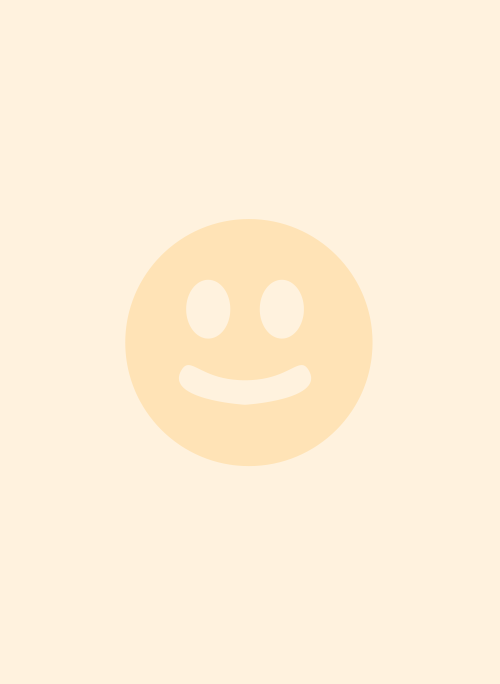「では、本当におこがましくはありますが、ゆきをお願いします。」
玄関でゆきの母親こと、柊弥生さんが深々と頭を下げた。
期限は2週間。
この家でゆきはおじいちゃんとの約束を探すのだ。
つまり、壊れかけた心を修復し、自分の足で人生を歩いて行けるように図る。
もちろんそれは大人たちの考え方だが、子供たちも薄々理解していた。
「ええ、こちらの但野さんはとても優秀な方ですから、私も息子をお願いしてる身ですけれど。」
「はい。何かあればすぐご連絡しますし、尽力します。」
それはもう爽やかに夏が請け負った。
「ゆきの服などは後で送りますが、食費などはまた後日持って参ります。」
「あらぁ、いいですよ、そんなこと。」
「え、でも…」
「春樹くんのお友達ですし、この家は元々柊さんの家ですから。我が家と思ってください。」
困ったように笑い、弥生はまた深くお辞儀した。
実際不安がないといえば嘘になる。
義父の家だったとはいえ、初めて会った人達に一人娘を預けるのだ。
お手伝いさんを雇うような立派な家柄なのだろうが、普段この家には春樹と夏だけ。
男所帯だ。
でも弥生には確信もあった。
接客業を長く勤める弥生は人を見る目だけは自負している。
宮前家はそのお目がねに適った。
もちろん夏も。
「ゆき、迷惑をかけないようにね?」
「うん…。ママ、ありがとう。」
ふんわりと、笑うと雰囲気ががらっと変わるゆき。
それを向けられた弥生ははたと気づいた。
義父が亡くなってから、初めて見せたゆきの可愛い笑顔。
久しぶりに見た娘の笑顔に、不安は一気に飛び去った。
「では、宜しくお願い申し上げます。」
「はい、お帰り、お気をつけて。」
車が凸凹道をゆっくり下っていく。
皆で見えなくなるまで見送った。