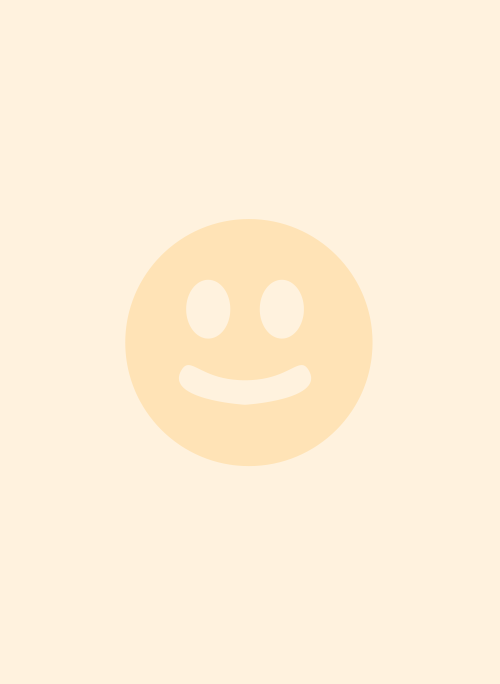挑むような目を向ける少女。
窓の外はとっくに闇に覆われて、街灯なんてひとつもない山の上。
微かに香る夕飯の匂いに似合わない微妙な空気。
敏感に感じ取ったのは、夏。
「差し出がましい事は承知で提案します。ゆきちゃん、おじいちゃんは多分約束を果たしてくれるよ。」
「…は?」
怪訝な顔をしたのはゆきの隣に座る母親。
「まぁ、但野さん。なにか名案でもありそうねぇ。」
ほんわか笑う母さん。
爽やかに笑顔を返し、夏は続けた。
「ええ、ゆきちゃんのおじいちゃんは嘘をつかない方なのでしたら、きっとどんな形であれ孫娘の声を聞いていると思います。
…だからゆきちゃん、おじいちゃんはもう探せないけど、
…おじいちゃんとの約束を探してみないか?」
「約束を?」
「そう。おじいちゃんとの約束がちゃんと果たされたか、その行方を探してみようってこと。」
しばらく思案していたゆきが小さく頷いた。
その様子に、母親は驚き、母さんは微笑み、春樹は抑えていた胸を撫で下ろした。
実はさっきから緊張した空気に呼吸がうまくできなくて、胸が苦しかったのだ。
まっさきに気づいたのは夏で、すかさずこの空気を緩和しにかかった。
「おし、じゃあ、その約束をしってるのはゆきちゃんだけだからね。どこに行ったら探せるかな?」
「…ここ。」
「ここ…ってこの家?」
こくんと頷くゆき。
遠慮がちに春樹と母親を見る。
「まぁ、それなら見つかるまでここに居たらいいわ。春樹くんもお友達が出来るしいいわよねぇ?」
「うん、もちろん。」
ゆきが可愛そうだとひどく同情していた春樹はすぐに答えた。
鶴の一声ならぬ夏の一声で、ゆきはおじいちゃんにもう会えないことを納得した。
本当にあっけなく。
もう探せない、探しても会えない。
でも、おじいちゃんとの約束を探すことはできる。
一体どんな約束事なのか。
それを知っているのはまだゆきだけだった。