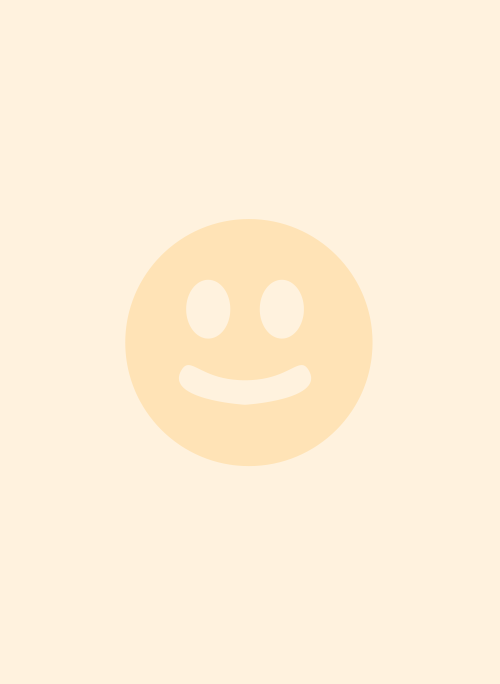頑なな少女はあくまでも、おじいちゃんに会うまでは態度を崩さないつもりらしい。
春樹に告げたように、紳士的で優しい祖父だったのだろう。孫娘がこれほど慕う人ならば、会ってみたかったなと春樹は思った。
しかしそれは叶わない。
ゆきにとっては耐え難い事実なはずだ。会ったことのない春樹だって、こんなに胸が苦しいのだから。
困惑した母親は大きくため息をついて、両手でゆきの頭を無理矢理上げさせた。
「ゆき、いいかげんにしてちょうだい!こんな…他人様に迷惑かけて!」
声を張り上げた母親に、泣いてぐちゃぐちゃな顔の少女。
見ていて気持ちのいいものではない。
なんとか穏便にならないかと春樹は口を開いた。
「…僕は…迷惑だなんて思ってないよ。」
「…そうね、ママも思ってないわ。」
優しく微笑んで同意したのは母さんだ。
「それで…ゆきちゃんはどうしたいのかな。」
おっとりと、なんでもないことのようにさらりと母さんがゆきに尋ねた。
「おじいちゃんに…会いたいの。約束したの。まだね…約束果たしてもらってないの…。」
「だから、ゆき。その約束ってなんなの。」
母親のその質問にはぎゅっと唇を引き結びうつむくだけだ。
「はぁ…、すみません。ずっとこんな調子で。何か義父と大切な約束をしたらしいんです。その内容は教えてくれないんですが…。」
亡くなった事を認められない程の約束。
果たされることのない約束。
約束をすぐ忘れるのは大人だけ。
まだ無垢で清らかな少女が心を捕われるには十分な理由だった。
「ゆきちゃん。」
母さんがゆきに、ゆきだけに話しかける。
春樹の母さんはとても優しい。どんな小さな事だって、まっすぐ向き合うのだ。
春樹の小さな日常の話しにも、小さな悩みや悲しみにも、春樹の小さな成長にも、まっすぐ向き合い話しを聞き、諭し、喜ぶ。
雰囲気だけでも場が和やかになる母さんに、ゆきも涙を留めて向き合った。
「ヒントをくれないかしら…。おじいちゃんとした約束の。」
「…ボタン。」
「そう…じゃあゆきちゃんはその約束、ちゃんとおじいちゃんは果たしてくれると思う。」
「おじいちゃんは、あたしに嘘ついたこと一度もない。」