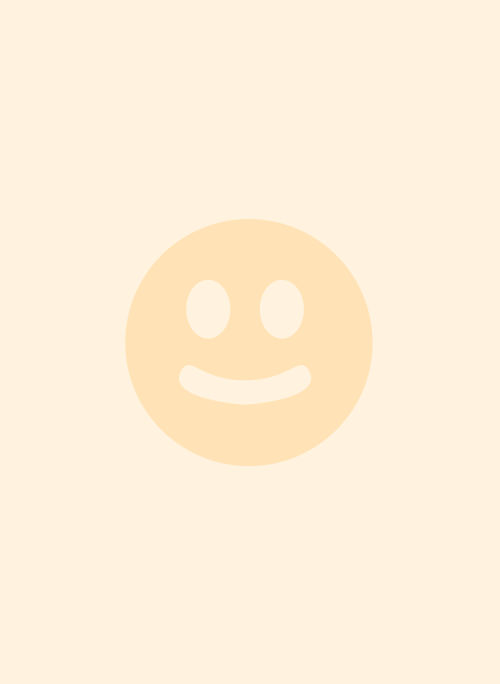「はい、母さん。お茶。」
にっこり微笑んでお茶を受け取り、母さんがこの重い空気を打ち破った。
「…柊さん、ですよね。」
「はい。このたびは娘のゆきがご迷惑おかけしまして、申し訳ありません。」
ふふ、と笑って母さんが首を傾げる。
「迷惑だなんて、とんでもない。こんな素敵なお家を建てた方のお孫さんが遊びに来てくださって光栄です。」
おっとりとした口調が場を和ませた。
ずっとクッションに顔を埋めたままのゆきがガバッと顔を上げた。
「おばさん、おじいちゃんのこと知ってるの。」
「ごめんなさいねぇ、おばさんはお会いした事はないの。でも、こんな素敵なお家を建てた方ですもの。とてもいいおじいちゃんなのね。」
「…うん。」
「あの…義父なんですが…」
ゆきの母親が口を挟む。
言いずらそうに声を低め、目を伏せて。
「亡くなったんです…。」
「えっ!」
驚いたのは春樹と夏だ。
ゆきはそんなこと一言も言っていなかった。
「…ええ、今日不動産屋に行きまして伺ってます。この度はご愁傷様で…」
「…いえ…」
母親同士、形式上の挨拶を交わし頭を下げた。
つられて隣に座っていた春樹もぺこりと首だけ傾けた。
「それで…この子にもきちんと話して聞かせたつもりだったんですが、どうにも納得してくれなくて…。」
ちらりと隣に視線を移す。
せっかく持ち上げた顔を再びクッションに埋めているゆき。
小柄な少女がさらに小さく萎んでいた。
「…とてもショックだったらしくて、記憶が混同してるみたいなんです。何度亡くなったことを諭しても、次の日には義父を探し回る始末で…。」
「まぁ…。」
同情と哀れみの目で母さんもゆきを見た。
もちろん春樹も夏も。
「…おじいちゃん。」
掠れた声がクッションから漏れた。
顔を見なくても泣いていると解る。
「…ゆき、おじいちゃんは亡くなったのよ。ゆきもちゃんとお葬式でお別れを言ったでしょう。」
そっと肩に回された母親の腕をいやいやと全身で拒んだ。
「…言ってないよ、お別れなんて。ここならきっとおじいちゃん帰ってくるよ。」