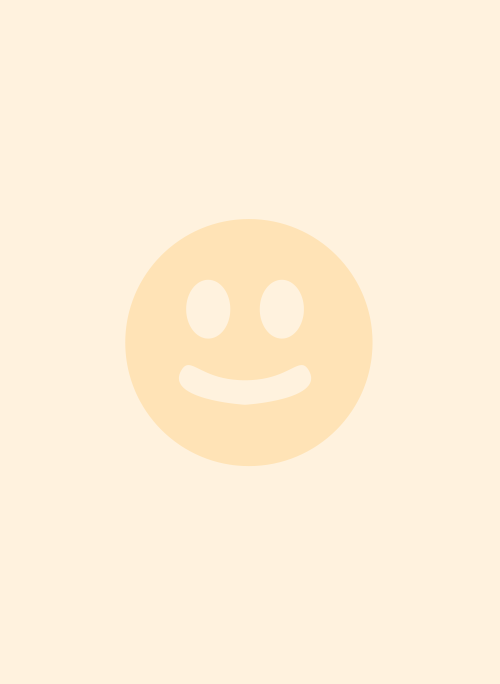おやつを食べ、春樹が入浴を済ませ、夕食が出来上がる頃。
外は夕日も沈み、微かに西の空が妖しく赤く染まる時刻。
インターホンが鳴った。
ピンポンピンポンと忙しなく連続的だった。
「…ゆきちゃんの…ご両親かな。」
くつくつと鍋の中でシチューが煮込まれている。
「母さん…ではないよね。」
母さんならこんな押しかたはしない。
かちっとコンロの火を消して、夏が玄関へ向かった。春樹も後を追った。
ゆきは、リビングソファーに腰掛け胸にクッションを抱えて顔を伏せている。
まだ押され続けるインターホンに夏が返事をし、玄関を開けた。
「ご連絡いただきました、柊です!あの、ゆきは!」
対面するなり勢いよく夏に迫ったのは綺麗な女の人。ゆきの母親だった。
「…中にいますよ。」
「ご迷惑おかけして、誠に申し訳ありません!
…ゆきっ!帰るわよ!」
玄関からまっすぐリビングに繋がる家なので、ソファーで小さくなっていたゆきをすぐに見つけたらしい。母の呼びかけに一瞬肩を揺らしただけで、ゆきはクッションに顔を埋めたままだ。
ゆきの反応がない事で再び声を張り上げようとする母親を制して、夏が言った。
「…いえ、少し落ち着いてください。とりあえず上がって頂いてもいいかな、春樹くん。」
「え、あ、うん。」
ゆきの母親のあまりの剣幕に、立ち尽くしていた春樹があわてて頷いた。
普段の春樹なら、どうぞおあがり下さい、と丁寧に迎えるのだが、今はそれどころではない。
代わりに夏が普段以上に丁寧な言葉を紡ぐ。
「家主がこう申しておりますので、どうぞお上がり下さいませ。」
「え。…ではお邪魔いたします。」
母親は少し目を泳がせ悩んだが、すぐに視線をまっすぐに戻した。
夏に頭を下げ、春樹に向き直りさらに深くお辞儀する。
そして玄関できちんと靴を揃え、遠慮なくといった様子でまっすぐリビングまでたどり着いた。
誰に促されることもなく、リビングソファーに腰を下ろす。ゆきの隣だ。
夏と春樹はそれぞれに、自分の役割をこなした。
夏はお茶菓子。
春樹はお茶。
ガラス板で、夏が編んだレースのクロスをされたリビングテーブルがにわかに華やぎ、話しをする準備が整った。
だが、誰が口火を切るものか。
気まずい雰囲気に飲まれそうになったとき、再び玄関から高い音が響いた。
どうやら春樹の母親も到着したようだ。