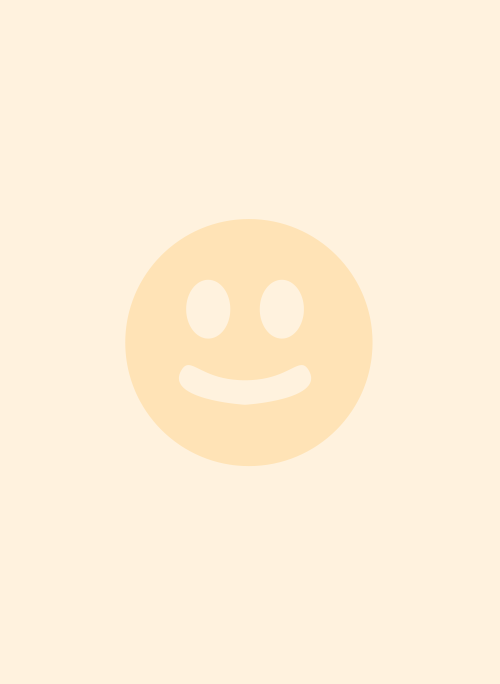「春樹くん、奥様が不動産屋に確認取って来るって。」
「え、母さん来るの。」
「ああ、今日は仕事抜けても問題ないらしい。」
また迷惑をかけてしまった、と落ち込む春樹に夏は微笑みかけた。もちろんにんまりと。
「奥様、春樹くんに会いたいから来るってさ。」
夏にはもう春樹が何を考えているか、表情だけで手に取るように分かる。
短い期間ではあるが、それだけ春樹は夏に心を許していた。
春樹はまだまだ夏の謎を解明できていないが。
「で、ゆきちゃんのご両親はいつ頃着くかな。」
「…車だったら3時間くらい。」
「えっ。そんなに遠いの。」
春樹が驚いて声を上げた。
「…ゆきちゃんはどうやってここまで来たのかな。」
「電車と、バス。」
「一人で!」
春樹は未だかつて電車にもバスにも一人で乗ったことがない。
移動はたいてい母さんの運転する車か、救急車なんて時もあった。
同世代の中で、春樹より救急車に乗った経験数が右にでるものはないかもしれない。
けど一人で電車やバスに乗れることのほうが、とても凄い事だと春樹には感じられた。
「すごいね!僕はひとりでなんて…きっと無理。」
中学生にもなれば一人で電車に乗ることなどなんてことない。
感嘆する春樹を不思議そうに眺めて、ゆきは首を傾げた。
「春樹…くんは、箱入り息子なの。」
あはは、と夏が吹き出す。
「そうかもね、春樹くん。」
「そ、そんなこと、」
ない、と言いかけて春樹は口をつぐんだ。
病気のせいもあるが、あの両親の過保護ぶり。
端から見れば十分箱入りだ。
「まぁ、それはいいとして。二人ともおやつにしようか。今日はシフォンケーキだよ。」
甘さひかえめの。
と付け足して夏はキッチンに向かう。
春樹はお茶の準備に立ち上がった。
最近ではお茶を煎れるのは春樹の役目になっていた。夏に丁寧に指導を賜り、緑茶でも紅茶でもハーブティーでも、春樹の煎れたお茶の方が美味しいと両親が絶賛し、夏が太鼓判を押したので、得意になってこれは僕の仕事だ、と宣言したのだ。