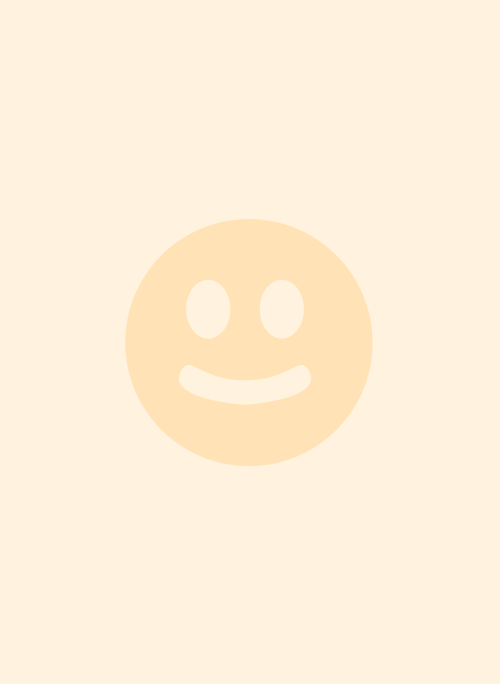綺麗に笑うのは、実は誰にでも出来ることじゃない。
愛想笑いや苦笑い。夏に至っては本気の笑顔すら上手にできないのだから。
春樹にとっての笑顔は、今生きていることを実感するためのツール。
「僕が天使なら、ゆきちゃんは女神様だね。」
春樹がなにげなく言った言葉を受けて、ゆきは赤面し、笑った。
久しぶりに柔らかな雰囲気をまとうゆき。
春樹の中で何かがスパークした。
「僕、ちょっとやらなきゃいけないことあるから、夏くんに言っておいて!」
玄関までたどり着いていた二人。
開けるなり、春樹は靴を脱ぎ捨てて二階の自室へ一目散。
突然の事にゆきは口をあんぐりあけて、その姿が扉の向こうに消えるのを見ていた。
「あれ?春樹くんは?」
「…やることあるって。」
「あっ、そう。」
ふーん、と鼻を鳴らして夏は冷蔵庫を開ける。
中には今日のおやつ。
バナナとショコラのカップケーキ。
甘いものが苦手な夏。
甘いものが好きな春樹。
美味しそうに食べるゆきを満足げに眺めていた夏だったが、やはり、と思い立って再び冷蔵庫を開ける。
冷気のもやは下へ下へと流れていて、一番下の段のカップケーキを包んでいる。
それを皿に乗せ、春樹の好きなミルクティーを甘くしないで煎れた。
うららかな春の午後。
紅茶とケーキ。
他に何を必要とするだろうか、満たされていく夏の気持ち。
「…春樹くん?入ってもいい?」
軽く扉を叩いてから、夏は春樹に呼び掛けた。
「どうぞ。」
開けると、机に向かう春樹の背中。
「なに?」
「おやつ、持ってきた。」
「え、わざわざ?ありがとう。」
「…何してんの?」
「ちょっと。」
「そろそろ教えてくれてもいいんじゃないかと、俺は思うよ。」
「うん…、」
「で、今は何してるとこ?」
春樹の手元を見ると、薄汚れた封筒を睨みつけているだけ。
「なに、それ?手紙?」
「ううん。」
「中身見たの?」
「ううん。」
「じゃあ…、」