帰りの車内は、2人とも無言だった。
私が話せる状態でなかったこともあるし、健さんも私に声をどうかけていいのか分からなかったらしい。
家に帰って、まず最初に私がしたことは、小説の更新だった。
どうしてそんなことをしたのかは、きっと私の生きた証を残したかったから。
死への恐怖がより強くなったこともある。
この作品を残して死なないと、私は忘れ去られてしまうかもしれない。
一心不乱に小説を書きあげる私を健さんは黙って見てた。
数時間かけて中途半端だった作品を終わりに近づけた。
これでもう、いつでも終わりにできる。
私を残すことが出来る。
携帯から手を話すと、ボロボロと涙がこぼれて身体が震える。
怖い。怖い。怖い。
死がこんなにも近くにあるなんて…
何も言わずに、そっと健さんが私を抱きしめる。
私は声を出して子供のように泣いた。
私が話せる状態でなかったこともあるし、健さんも私に声をどうかけていいのか分からなかったらしい。
家に帰って、まず最初に私がしたことは、小説の更新だった。
どうしてそんなことをしたのかは、きっと私の生きた証を残したかったから。
死への恐怖がより強くなったこともある。
この作品を残して死なないと、私は忘れ去られてしまうかもしれない。
一心不乱に小説を書きあげる私を健さんは黙って見てた。
数時間かけて中途半端だった作品を終わりに近づけた。
これでもう、いつでも終わりにできる。
私を残すことが出来る。
携帯から手を話すと、ボロボロと涙がこぼれて身体が震える。
怖い。怖い。怖い。
死がこんなにも近くにあるなんて…
何も言わずに、そっと健さんが私を抱きしめる。
私は声を出して子供のように泣いた。



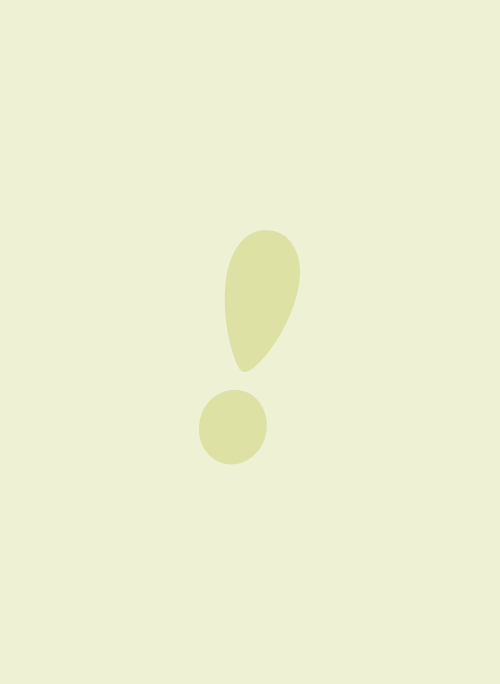
![[実話]16歳〜私の生きた道〜](https://www.no-ichigo.jp/img/issuedProduct/365-124.png)
