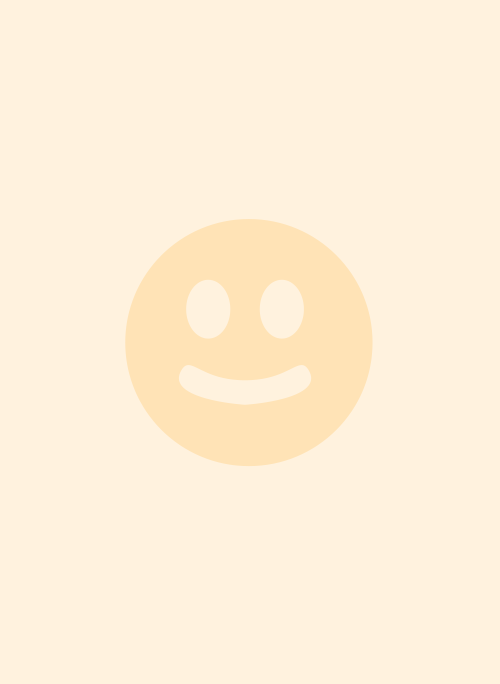恐れていた瞬間は、あまりにもあっさりとやってきた。
忍び足で近づいてきたかのように、突如現れ、受け入れる側の意思とは何の関係もなく、全てを奪い去って行った。
その日は登校日で、わたしは女学校の制服を着ていた。
家に帰ると、それぞれ出払っていたらしく誰もいなくて、わたしは着替えるのも億劫だったのでそのままいつもの場所へ向かうことにした。
道すがらも考えるのは彼ひとりのことばかり。
わたし自身が出てくるのは、先のことを想像する時ではなく、過去の日々を振り返る時だけだった。
岬近くに到着し、波に濡れながら岩場を渡って砂浜の上に立つ。
予想していなかったことだったのだが、わたしが来た時、既に砂浜には彼が座っていた。
亜麻色の髪がなびいて、彼の横顔が見える。
真っ直ぐにひき結ばれた唇と何も映していないように虚ろな瞳。
彼のうつくしい横顔に浮かんだその表情を見た途端、わたしはたった数日前に立てた誓いをいとも簡単に破り、はらりと涙を流していた。
頬を伝う感触にぎょっとする。いつからわたしはこんな泣き虫に?
少し日焼けした腕でぐいと拭って、思いきり息を吸いこんでから、彼に声をかけた。
「ティート!」
彼は振り向いてわたしに笑顔を見せた。ここ最近見慣れた表情。痛ましいぐらい上手な笑顔。
わたしは駆け寄り、ティートの隣に腰をおろした。
いつも通りに接してみようと思ったのに、どうしても彼のような表情が作れない。
口を開いても、その笑顔を間近で見てしまうと唇が震えるばかりだ。
悟りかけているわたしの様子を見て取ったらしく、ティートは張りつめた笑顔から少しだけ力を抜いて、わたしをみつめ続けた。
笑顔の作り方を忘れてしまったかのようだ。
ならばせめて、と、涙だけはじっとこらえたままに、わたしもティートをじっとみつめた。
海鳥の声と潮のさざめき。
二人の浜辺には、不安ともうひとつ、避けられない悲しみがそこらじゅうに散らばっていた。
忍び足で近づいてきたかのように、突如現れ、受け入れる側の意思とは何の関係もなく、全てを奪い去って行った。
その日は登校日で、わたしは女学校の制服を着ていた。
家に帰ると、それぞれ出払っていたらしく誰もいなくて、わたしは着替えるのも億劫だったのでそのままいつもの場所へ向かうことにした。
道すがらも考えるのは彼ひとりのことばかり。
わたし自身が出てくるのは、先のことを想像する時ではなく、過去の日々を振り返る時だけだった。
岬近くに到着し、波に濡れながら岩場を渡って砂浜の上に立つ。
予想していなかったことだったのだが、わたしが来た時、既に砂浜には彼が座っていた。
亜麻色の髪がなびいて、彼の横顔が見える。
真っ直ぐにひき結ばれた唇と何も映していないように虚ろな瞳。
彼のうつくしい横顔に浮かんだその表情を見た途端、わたしはたった数日前に立てた誓いをいとも簡単に破り、はらりと涙を流していた。
頬を伝う感触にぎょっとする。いつからわたしはこんな泣き虫に?
少し日焼けした腕でぐいと拭って、思いきり息を吸いこんでから、彼に声をかけた。
「ティート!」
彼は振り向いてわたしに笑顔を見せた。ここ最近見慣れた表情。痛ましいぐらい上手な笑顔。
わたしは駆け寄り、ティートの隣に腰をおろした。
いつも通りに接してみようと思ったのに、どうしても彼のような表情が作れない。
口を開いても、その笑顔を間近で見てしまうと唇が震えるばかりだ。
悟りかけているわたしの様子を見て取ったらしく、ティートは張りつめた笑顔から少しだけ力を抜いて、わたしをみつめ続けた。
笑顔の作り方を忘れてしまったかのようだ。
ならばせめて、と、涙だけはじっとこらえたままに、わたしもティートをじっとみつめた。
海鳥の声と潮のさざめき。
二人の浜辺には、不安ともうひとつ、避けられない悲しみがそこらじゅうに散らばっていた。