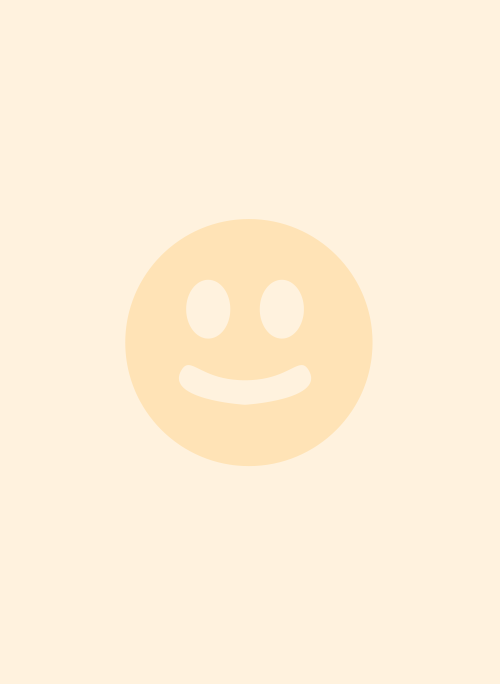寂しい時間にわたしは独りで考えた。
自分は彼に何を求めているのだろう。
うつくしく優しい、自分とは違った生き物のことを考えるのにはなんの問題もなかった。
だけど、彼と自分とのことを考えるという行為は、わたしにはとてもできなかった。
「未来」を考えるのが怖かったのだ。
小娘とはいえ数年も経てば成人する。
何の保障もない「永遠」を信じるには年をとりすぎていた。
生まれて以来ずっとそばにあった海という場所。
生活の一部となった、色、音、香り。
わたしは二人の秘密の場所である洞くつに隣接した、一人では広く感じる浜辺に寝っ転がった。
阿呆のように晴れた空を見る。
海とはまた違った青色が冴え冴えと広がり、その果ては見えそうもない。
空よりは海がいい、と思って上体を起こす。
両手で顔を覆って、泣いた。
はしたないことだとは思ったけど止められない。涙がぼろぼろと転がって、腕を伝って肘から垂れて、砂浜の上まで到達する。
わからなかった。怖かった。
一人の浜辺には不安しか見つけられなかった。
頼りどころがひとつもない。
二人で交わした約束なんてものはあるはずもなく、交わしたのは生まれてすぐの言葉だけだ。
心のどこかでは、会わなければよかった、とさえ思った。
こんなことを思いたくはなかったけれど。
不本意な思いが満ちてゆくのをとどめることができないのは、年端もいかぬ女学生の心の弱さだ。
赤ん坊のように泣いて泣いて、しゃくりあげながら泣きやんだあと、二度となくまいと心に誓った。
ことにティートの前では。
決して。
重たい誓いを胸に掲げて、わたしはその日、彼を待たずに家までの道を思いきり翔けた。
自分は彼に何を求めているのだろう。
うつくしく優しい、自分とは違った生き物のことを考えるのにはなんの問題もなかった。
だけど、彼と自分とのことを考えるという行為は、わたしにはとてもできなかった。
「未来」を考えるのが怖かったのだ。
小娘とはいえ数年も経てば成人する。
何の保障もない「永遠」を信じるには年をとりすぎていた。
生まれて以来ずっとそばにあった海という場所。
生活の一部となった、色、音、香り。
わたしは二人の秘密の場所である洞くつに隣接した、一人では広く感じる浜辺に寝っ転がった。
阿呆のように晴れた空を見る。
海とはまた違った青色が冴え冴えと広がり、その果ては見えそうもない。
空よりは海がいい、と思って上体を起こす。
両手で顔を覆って、泣いた。
はしたないことだとは思ったけど止められない。涙がぼろぼろと転がって、腕を伝って肘から垂れて、砂浜の上まで到達する。
わからなかった。怖かった。
一人の浜辺には不安しか見つけられなかった。
頼りどころがひとつもない。
二人で交わした約束なんてものはあるはずもなく、交わしたのは生まれてすぐの言葉だけだ。
心のどこかでは、会わなければよかった、とさえ思った。
こんなことを思いたくはなかったけれど。
不本意な思いが満ちてゆくのをとどめることができないのは、年端もいかぬ女学生の心の弱さだ。
赤ん坊のように泣いて泣いて、しゃくりあげながら泣きやんだあと、二度となくまいと心に誓った。
ことにティートの前では。
決して。
重たい誓いを胸に掲げて、わたしはその日、彼を待たずに家までの道を思いきり翔けた。