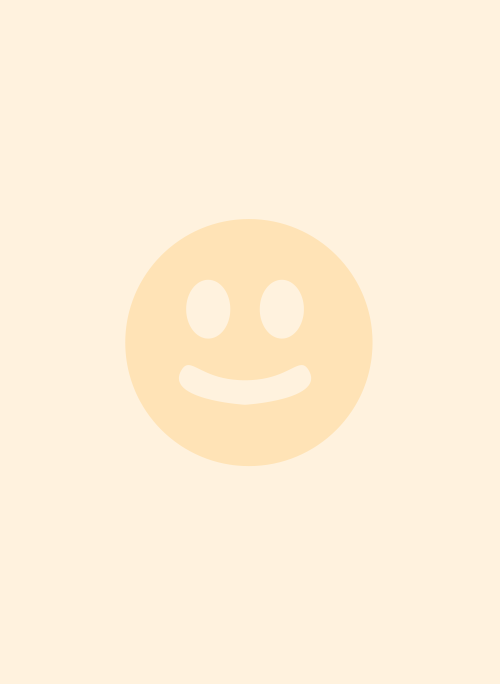夏期休暇が始まって数日が経った。
やはりティートはあれ以来、会うたびにやつれていくような気がしてならなかった。
それを口に出しても、彼は必ず否定した。否定したというよりは肯定をしなかった。
あまり何度も同じことを尋ねられるのはいい気分ではないだろうと思ったので、わたしは気にしないふりをすることにした。
数週間前よりも口数の減ったティートの代わりはわたしがする。
彼と会うことが日常になっていたわたしにとって、「変化」ほど怖いものはなかった。
正直を言うと、わたしも少し無理をしていた。
「静ぅ、最近しょっちゅう、どっか行っとるの?」
級友の公美子と一緒に、学校の水遣り当番をしていた時だった。
公美子は女学校に入った頃からの友達で一番仲がいい。
山側に住んでいる彼女とは家が遠いにも関わらず、いつもどちらかの家で一緒に勉強をしていた。
「昨日の夕方頃に家に行って、しばらくおらしてもらってたけど、帰ってこんから」
「ほんまにい? ごめんなあ」
笑ってごまかして、言い訳を考えようとするけれど頭が働かなかった。
ティートの負担を減らすために、わたしはいつも同じ時間に洞くつに行くことにしていた。
夕日が海に溶ける頃。
だけど会えないことも多くて、そういう日の次の日には、午前と午後の二度も洞くつに行ってみたりする。
若さと誰かを思う心は何にも勝る活力源なのだ。
「時々、ぼおっとしとるみたいやし。何、もしかして、格好良い男の子でも見つけたん?」
返事に詰まるわたしに気を遣ったのか、公美子はわざと軽い調子で言ってわたしをこづいた。
「静に好きな人ができたら、わたしに一番に紹介しいや」
「わかったて。公美子もやで」
明るく笑ってくれた公美子につられてわたしも笑う。
暑い夏の日、中庭の中心で金属のじょうろを振り回して、わたしは大事な級友に一生果たせない約束をしてしまった。
やはりティートはあれ以来、会うたびにやつれていくような気がしてならなかった。
それを口に出しても、彼は必ず否定した。否定したというよりは肯定をしなかった。
あまり何度も同じことを尋ねられるのはいい気分ではないだろうと思ったので、わたしは気にしないふりをすることにした。
数週間前よりも口数の減ったティートの代わりはわたしがする。
彼と会うことが日常になっていたわたしにとって、「変化」ほど怖いものはなかった。
正直を言うと、わたしも少し無理をしていた。
「静ぅ、最近しょっちゅう、どっか行っとるの?」
級友の公美子と一緒に、学校の水遣り当番をしていた時だった。
公美子は女学校に入った頃からの友達で一番仲がいい。
山側に住んでいる彼女とは家が遠いにも関わらず、いつもどちらかの家で一緒に勉強をしていた。
「昨日の夕方頃に家に行って、しばらくおらしてもらってたけど、帰ってこんから」
「ほんまにい? ごめんなあ」
笑ってごまかして、言い訳を考えようとするけれど頭が働かなかった。
ティートの負担を減らすために、わたしはいつも同じ時間に洞くつに行くことにしていた。
夕日が海に溶ける頃。
だけど会えないことも多くて、そういう日の次の日には、午前と午後の二度も洞くつに行ってみたりする。
若さと誰かを思う心は何にも勝る活力源なのだ。
「時々、ぼおっとしとるみたいやし。何、もしかして、格好良い男の子でも見つけたん?」
返事に詰まるわたしに気を遣ったのか、公美子はわざと軽い調子で言ってわたしをこづいた。
「静に好きな人ができたら、わたしに一番に紹介しいや」
「わかったて。公美子もやで」
明るく笑ってくれた公美子につられてわたしも笑う。
暑い夏の日、中庭の中心で金属のじょうろを振り回して、わたしは大事な級友に一生果たせない約束をしてしまった。