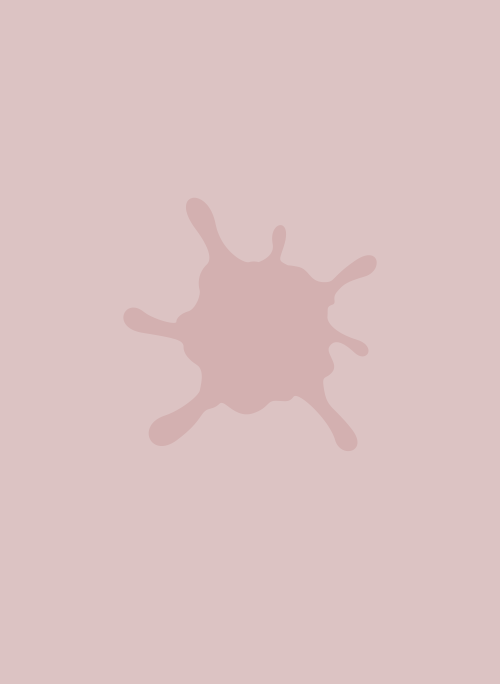「心配いらないよ。俺が野田さんのこと、幸せにしてやるから」
「………」
吐き気を催した。
背中に虫酸が走ったような嫌悪感が身体中を駆け巡り、膝がガクガクと震えた。
その場に立っているのがやっとで、次に何か言われたら、私の頭はおかしくなりそうだった。
彼氏がいないから諦めきれないという彼に、もう最終手段しか残っていなかった。
それは……彼氏を作ること、だ。
「………」
吐き気を催した。
背中に虫酸が走ったような嫌悪感が身体中を駆け巡り、膝がガクガクと震えた。
その場に立っているのがやっとで、次に何か言われたら、私の頭はおかしくなりそうだった。
彼氏がいないから諦めきれないという彼に、もう最終手段しか残っていなかった。
それは……彼氏を作ること、だ。