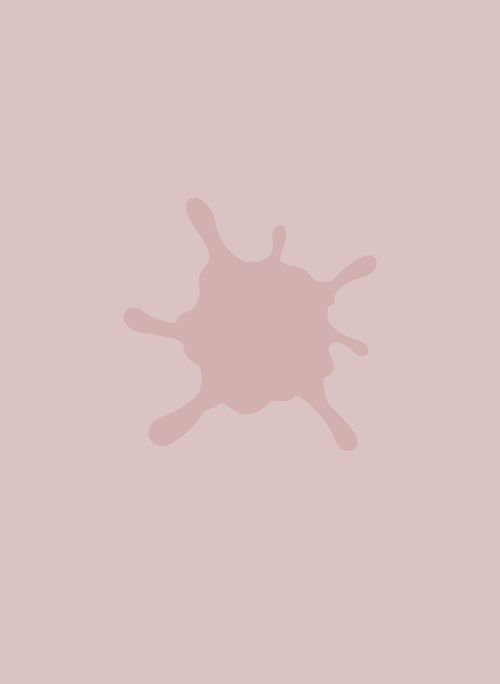「王子、それはもしや、プロポ……」
「とっくにした! 君は生涯私の花乙女であると誓った。父王はそれで君をあきらめた。私のものである印を贈った。サファイアの指輪だ。鈍い君のことだ、どこかにうち捨ててしまったろうが……」
アレキサンドラはチュニックの上からそれが間違いなくあるのを確かめた。首から鎖ごとそれを引き出すと、王子にさしのべた。
「これ、ですね?」
「ああ、受け取っていてくれたのか」
「お返しいたします。わたくしはいろんな場所で、場面で、助けていただきながら、なんの返礼もしませんでした。できなかったのです」
彼女は嗚咽した。