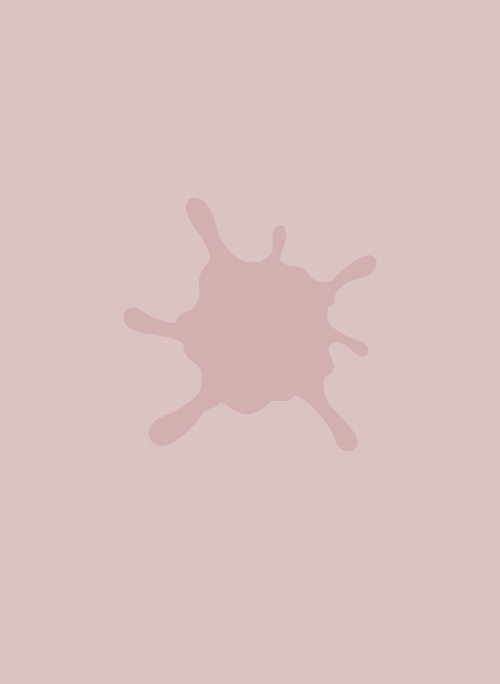「なぜです」
「なぜ、と問うのか? あんな目にあったのだ、彼なら腐っているかもしれないだろう」
思いもしない返答に、アレキサンドラの心は大きく揺らぎ、思わずくすっと笑ってしまった。
「もしかしたら、冥府の王になるべく、勇ましく君臨しているかもしれません」
「そちらの方が良いのか、君にとって彼は」
王子はにやり、として言った。
「どちらにしろ、意気消沈している姿は、見たくありません。あの宰相殿の弟君ですから」
「嫌味(イヤミ)のキレは兄弟そろって良いんだがな」
「よっぽどきついことを言われてるんですね」